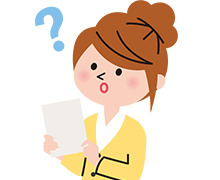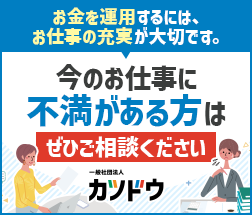これから買おうとしている投資信託がどんなコンセプトで作られている商品なのかを理解するための資料、それが目論見書です。
目論見書には2種類あり、一つは投資家が請求した時にだけ交付される請求目論見書、もう一つは金融機関が投資家に対して交付するよう法律で義務付けられている交付目論見書です。
請求目論見書はページ数も情報量も多く、読むのに骨が折れますが、交付目論見書は大切な内容に絞り込んで書かれているうえ、フォーマットも決まっているので、投資に慣れていない人でも理解しやすくなっています。
しかし理解できても、どう役立てればいいのかまではわからないという人も多いのではないでしょうか。
そこでここでは、交付目論見書の各項目について、投資判断に活用するための読み方を解説します。
商品分類および属性区分
商品分類
| 商品分類 | ||||
| 単位型・追加型 | 投資対象地域 | 投資対象資産(収益の源泉) | 独立区分 | 補足分類 |
| 単位型投信・追加型投信 | 国内・海外・内外 | 株式・債券・不動産投信・その他資産・資産複合 | MMF・MRF・ETF | インデックス型・特殊型 |
単位型・追加型
単位型投信というのは、一定の募集期間しか購入できない投資信託のことで、追加型投信というのはいつでも購入できる投資信託を指します。
まとまった資金があれば単位型投信で資産を形成することも可能ですが、毎月の給料から少しずつ積み立てていきたいという人は、追加型投信を選ぶ必要があります。
投資対象地域
投資対象地域は文字通り、どの地域を対象に投資をするかを示す項目です。
どの地域を投資の主軸に置くのかは人それぞれです。
バランスを取りたいという人は国内と海外に同時に投資できる「内外」の投資信託を選ぶのもアリです。
いずれの場合にしろ、今買おうとしている投資信託が自分の方針に合う地域に投資する商品なのかどうかは確認しておきましょう。
ちなみに、「新しい投資先」として海外投資が最適な2つの理由を簡単解説などでも解説しているように、お金の窓口ではリターン重視の人でも、リスク重視の人でも、今後は海外への投資を視野に入れることをおすすめしています。
独立区分・補足分類
表の右側二つ、独立区分と補足分類は該当する商品にだけ記載される項目です。
MMFはマネー・マネージメント・ファンドのことで、公社債を対象にした投資信託の一つを指します。
MRFはマネー・リザーブ・ファンドのことで、こちらも公社債投資信託ですが、MMFよりも安全性の高い公社債等に投資する商品です。
ETFは上場投資信託のことで、日経平均株価などの指標に連動するように運用される商品となっています。
補足分類の項目には指標に連動するよう運用する場合はインデックス型、指標を上回るパフォーマンスを目指すアクティブ型のような運用をする場合は特殊型と記載されます。
「リスクの低さを重視する」「多少リスクは高くても、より高いリターンを狙う」など投資の方針は様々ですが、商品分類を見るだけでもその商品が自分の方針にあったものかどうかがわかるようになっているのです。
属性区分
| 属性区分 | ||||||
| 投資対象資産 | 決算頻度 | 決算対象地域 | 投資形態 | 為替ヘッジ | 対象インデックス | 特殊型 |
| 株式、債券、不動産投資、資産複合など | 年1回、2回、4回など | グローバル、日本、北米、アジア、エマージングなど | ファミリー・ファンド、ファンド・オブ・ファンズ | あり・なし | 日経225・TOPIX・その他 | 条件付運用型、絶対収益追求型など |
商品分類の横、もしくは下に記載されているのが上表の属性区分です。商品分類よりもさらに詳しく投資信託のコンセプトについて説明する部分です。
たとえば決算対象地域なら、手堅い投資をしたいのにエマージング(新興国)になっていたり、大きなリターンを狙いたいのに日本になっていたりすれば、その商品が自分の求めているものではないということがわかります。
ファンドの目的・特色
次の項目である「ファンドの目的・特色」では、より具体的に商品の仕組みやコンセプトが説明されています。
インデックス型の投資信託の場合は、概ね「○○に連動する運用を目指す」という内容で終始していますが、アクティブ型の投資信託の場合は商品の色が一番濃く出る項目となっています。
たとえば投資対象地域が「内外」の商品であれば、具体的にどの地域にどれくらいの割合で資産を分散して投資するのか。
投資対象資産(収益の源泉)が「資産複合」であればどんな資産をどんな配分で投資するのか。
あるいはどんなプロセスで投資する地域や資産、その配分を変更していくのか(あるいは変更しないのか)。
そういった情報がファンドの目的・特色の項目には書かれています。
ここでは自分の投資方針と合っているかどうかを確認するのはもちろんですが、説明されている内容が理解できるかどうかも大切です。
というのも、ファンドの目的・特色の説明で仕組みが理解できない商品は、得てして自分にとって複雑すぎる商品だからです。
知らないと損するお金の歴史「リーマン・ショック」でも説明したように、複雑すぎる金融商品はリスクの予想がつかず、大きな損失につながる危険も高くなりがちです。
そのためインデックス型の投資信託を検討する場合は、ファンドの目的・特色の項目をよく読むようにしましょう。
投資リスク
投資信託の価値(基準価額)がどのような要因で変動するのかについて説明する部分です。
主な要因は信用リスク、価格変動リスク、為替変動リスク、カントリーリスクの4種類。
これらのリスクの概要と、リスクへの対策については「投資は怖い」と思っている人に知っておいて欲しい、「ギャンブル」との違いで詳しく解説しているため、ここでは割愛します。
運用実績
ここまで読んで「自分の投資方針に合った商品みたいだ」と思ってしまうと、間違った判断を下しかねません。
なぜなら商品の良し悪しは、「運用実績」の内容で決まるからです。
この項目には基準価額や純資産総額の推移、分配金の実績などが書かれています。
基本的には良い商品ほど純資産総額が増加傾向にあり、分配金をあまり出していない場合が多い傾向にあります。
また運用が始まった直後で運用実績がなかったり、少なかったりする場合は、良し悪しを判断することができないので、よほど自分の判断力に自信がない限りは買わない方が良いでしょう。
なお純資産総額の推移についての詳しい見方は、投資信託の「純資産額」は30億円がボーダーライン!活用法や注意点を解説を参照してください。
手続・手数料等
手続・手数料等の項目は大きく「お申し込みメモ」と「ファンドの費用・税金」の二つに分かれています。
お申し込みメモで確認しておくべきは「信託期間」です。
長期運用が目的の人は、原則「無期限」になっているものを選びましょう。
というのも投資信託の中にはたとえば「2025年12月」といったように運用期間が決まっているものがあるからです。
短期の運用しか考えていないのであれば問題ないかもしれませんが、長期で運用しようと考えている人にとっては途中で満期を迎える投資信託を買うよりも、ずっと運用してくれる投資信託を買う方が良いでしょう。
もう一点見ておくべきが「繰上償還」です。繰上償還とは信託期間が終了する前に運用が終了することを指します。
交付目論見書のこの項目には、どのような場合に繰上償還が行われるかが記載されています。
自分が計画している運用期間中に繰上償還されるようなことがあれば、資産運用の計画に支障が出る可能性があります。
あらかじめ投資信託の運用が終了する条件を確認しておきましょう。
ファンドの費用・税金では投資信託の購入・保有に必要な手数料などについて説明されています。
これも着実に資産を増やしていくためには必ず確認しておくべき項目です。
投資信託の費用については、別途数%が大きな差に!投資信託の手数料について知っておこうで詳しく説明しているので、こちらを参照してください。
まとめ
投資初心者のなかには、「今人気だから」「銀行の窓口の人に勧められたから」といった理由で、商品の内容をよく理解しないまま投資信託を選んでしまう人も少なくありません。
しかし「自分でよくわかっていない投資信託を買う」ということは、「リスクを理解しないままお金を使う」ということです。
そうしたお金の使い方をしていると、どうしても損をする危険性も高くなってしまいます。
交付目論見書は、「どんなコンセプトで運用されるのか」「どんなリスクがあるのか」といった投資信託の基本設計を理解するためにとても役に立つ資料です。
余計なリスクを背負わないために、また自分の投資方針に沿った商品を選ぶために、交付目論見書はしっかりと読み込むようにしましょう。