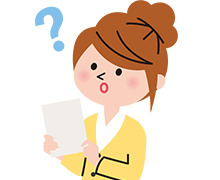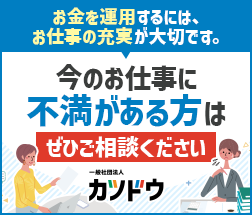こちらの記事では、株式とその歴史についてお話します。
株式投資は、最も有名な投資方法の1つです。
既にされている方も、これからやってみたいという方もたくさんいらっしゃるかと思います。
ところが、株ってどのように生まれたのか?どんな歴史があるのかって、知っている方はかなり少ないのではないでしょうか。
現在、株式投資を検討している方や、まだ検討中の方も、株式が誕生した理由を知っておくことで、投資への理解や判断に役立てることができます。
そこで、この記事では、
「そもそも株式ってなに?」
「株式はどんな目的でつくられたものなの?」
以上のような疑問を持っているあなたへ向けて、投資で取引されている商品の中でも代表的な株式の成り立ちについて紹介していきます。
株式が誕生した理由をやメリットを知ることで、投資についての理解や判断に役立てることができます。
具体的に紹介する内容は以下のものになります。
- そもそも株式とはなにか?
- 世界の株式の歴史
- 日本の株式の歴史
この記事は5分くらいでカンタンに読めて、株式の歴史や、つくられた目的について十分に知ることができますので、ぜひご一読ください。
そもそも株式とはなにか?

ここでは、「そもそも株式とはどんなものなのか」についてを紹介していきます。
一言でまとめると、株式とは”事業に必要な資金調達の方法”です。
会社が事業をはじめるためには、最低限の資金が必要になります。
しかし、事業に必要な資金は、大体の場合において巨額で、会社経営者個人が持っている資金だけでは足りないことがほとんどです。
この足りない事業資金を集めるための方法として、株式というものを発行して投資家に購入してもらいます。
株式は、会社が事業をはじめるときに、手元にある資金だけでは足りない場合に発行するもので、購入することで投資家は、その会社のオーナーになれる権利を手に入れることができるのです。
株式を購入した投資家は「株主」と呼ばれます。
また、投資家に株式を購入してもらい、集めた資金で事業を運営する形態の会社を「株式会社」といいます。
株式を購入するメリットは、毎年利益の一部を「配当金」や「優待」という形で、株主に還元してくれるという点です。
株式は誕生してから、資金を効率的に集める方法として支持され、現代の資本主義経済の発展に大きく貢献しているのです。
次からは、株式が誕生した理由や、世界でどのように株式が活用されたかについて、歴史を紹介していきますね。
世界の株式の歴史
ここから、株式が誕生から発展までの歴史を、順を追って紹介していきます。
株式は、大航海時代と呼ばれる17世紀のヨーロッパで発明されました。
15~17世紀のヨーロッパ人が、資源の獲得のために、航海・探検をして海外進出を行った時代のこと
新航路を発見した後、アフリカやアジア、新大陸と、世界各地へ進出して貿易、もしくは現地の資源の収奪を行った
なぜ、この大航海時代のヨーロッパで株式が発明されたのか、理由を説明していきますね。
大航海時代のヨーロッパ人は、自国では手に入らない香辛料などの貴重な資源を獲得しに世界各地へ進出していました。
この世界各地への進出に必要な資金集めは、航海をするたびに、ヨーロッパの中の裕福な人物たちから出資者を募って行われていました。
しかし、一人もしくは数人の資産家のみが行う融資は、当時非常にリスクの高いこととなっていました。
理由としては、当時の航海は、難破や海賊、疫病への感染などのリスクで、成功率は20%以下ともいわれるほどに危険なものだったからです。
自分の持つ資金を、成功確率が低い事業への投資に使いたいと思う資産家はいません。
そこで、航海をしようと考えていた探検家たちは、一部の大資産家からではなく、大人数の小資産家から融資をしてもらうために、株式会社を設立しました。
探検家たちが設立した株式会社では、株式を発行して大人数の出資者を募り、集めた資金で複数回の航海をして、得た利益を配当します。
この方法でなら、全部で5回の航海のうち1回しか成功しなくても、トータルで利益が出ていれば配当がもらえるので、出資者にとっても損失はありません。
1602年に設立された世界初の株式会社「オランダ東インド会社」は、この株式の仕組みを有効活用して、航海に必要な資金を効率よく集め、アジアでの貿易を独占しました。
オランダ東インド会社の成功によって、オランダの株式の取引が活発化して、首都アムステルダムは17世紀ヨーロッパの金融の中心地になりました。
しかし、17世紀後半に複数回起きたイギリスとの戦争や、1803年から起きたナポレオン戦争によってオランダの国力は疲弊して、金融市場としての活発な動きは失われていきました。
国力の衰退したオランダに変わって、海上貿易の覇権を握ったイギリスが、18世紀の後半から、株式をはじめとした金融市場の世界的な中心地になったのです。
産業革命が起こり、資本主義が発展した19世紀のイギリスでは、株式会社に関する法整備が進みました。
そして1844年には、イギリスで登記法が制定され、必要な要件を満たせば誰でも株式会社を設立できるようになります。
19世紀中頃に、イギリスでは登記法以外にも、株式会社の設立・運営に必要な各種の法整備が進み、現代の世界で使用されている株式会社制度が完成したのです。
株式会社の制度は、19世紀末にイギリスにかわって世界経済のリーダーになったアメリカで大きく発展しました。
1914年~1918年に勃発した第一次世界大戦で、戦場になったヨーロッパに対して融資をしていたアメリカは、戦後、世界の金融市場の中心地となり、株式の投資も世界で最も活発な国となりました。
アメリカでは、企業の合同によって、株式会社の巨大化が進み、わずか200社の株式会社に国家経済の22%、また株式会社の富の49.2%が集中するようになります。(出典:株式会社の歴史・理論・課題)
これらの巨大株式会社は、株主ではなく、経営者が直接支配する傾向が強く、当時のアメリカでは、従来の株式会社=株主の所有物という考え方が大きく変化していくことになりました。
そして次第にアメリカでは、株式会社は、投資家がより豊かになるための仕組みとしてよりも、国の統治のためになくてはならない社会制度として見なされるようになります。
1960年代~70年代になると、アメリカの株式会社の株主の比率は、個人から年金基金などの機関による投資家に大きく傾くことになります。
年金基金は、労働者から集めた資金によって、株式に投資していたので、アメリカでは株式会社の所有者は労働者であるという認識が定着しました。
ただし、株式会社の経営を直接的に支配しているのは、株主ではなく経営者であるという構造に大きな変化はありませんでした。
しかし、1980年代になると、アメリカ経済は巨額の財政赤字を抱え込むことになり、企業買収や、企業業績の低迷を原因とした不祥事が相次ぎ、「株式会社は誰のものか」が厳しく問われるようになります。
そして新自由主義という経済思想に基づき、「株式会社は株主のものである」という価値観が主流になり、株主の利益を最優先にして会社経営が行われるように変化していきました。
政府が企業に対して行う規制を緩和・撤廃して、民間の自由で活発な力に任せて経済成長をするという経済思想
巨額の富を持つ資本家や、競争力の強い企業の利益拡大を促進する一方で、雇用者のリストラや公共料金の値上げなどが引き起こってしまい、中流~下流層の生活を困窮させてしまうというリスクを持つ
アメリカでは、1990年代~現在まで、新自由主義的な経済政策の導入によって、株主重視の株式会社経営が行われており、株主がより大きな富を得られるような環境になっています。
次からは、我が国日本の株式の歴史から現在の状況までを紹介していきます。
日本の株式の歴史
ここから、日本の株式の誕生から現在までの歴史を紹介してきます。
日本では、証券取引の仕組み自体は、江戸時代の米の取引で利用されていました。
しかし、当時は戦争などの大規模な資金を集める必要がなかったため、株式の仕組みはまだ存在しませんでした。
その後、明治時代になり、先進国であった欧米の社会システムを取り入れ国内を発展させようとしたときに、近代的な株式の仕組みも同時に導入することになります。
1878年に株式取引所条例が制定されてから、東京や大阪で株式取引所が開設されました。
当時の株式取引所では国債の取引が中心で、株式の取引は、鉄道や電力など、ごく一部の大企業のものに限られ、株式を自由に発行できる市場はまだ存在しませんでした。
第一次世界大戦中の大戦景気のときには、物資の大量輸出による経済拡大で、日本では株式の取引が活発化しました。
第一次世界大戦中に、参戦国でありながら本土が戦場にならなかった日本が、戦場となった欧州諸国に大量の商品を輸出したことで発生した好景気のこと
しかし、戦後には輸出物資の需要がなくなった反動で起きた経済恐慌や、1923年に起こった関東大震災が原因の金融恐慌、そして1929年に起きた世界恐慌などで、株式市場は長期の低迷に見舞われます。
日本の株式市場の本格的な活発化は、第二次世界大戦後まで待たなければなりませんでした。
1945年の終戦後に、GHQ(連合国軍総司令部)から出された財閥解体令をきっかけに、それまで一部の巨大資産家だけが保有していた大量の株式が民間に放出され、株式市場は一気に活発化します。
1950年に勃発した朝鮮戦争の特需により、民間からの株式投資は急速に大衆化していくようになりました。
1960年代からはじまった高度成長期には、企業が事業をするための資金集めの手段は、投資家に株式を購入してもらうよりも、銀行からの借り入れが主流となっていました。
しかし、1979年に外為法が改正され、国内外の資本取引が自由化されたことで、外国人投資家による日本株の購入がブームとなり、国内株式市場は活発化しました。
日本と外国の取引に対して、必要最小限度の管理・調整を行うことで、体外取引の正常な発展や通貨の価値の安定を図り、経済の発展を促進させるための法律
正式名称「外国為替及び外国貿易法」
また、1980年代の円高・低金利・原油安という経済状況により、日本国内で発行されている株式の購入ブームが到来しました。
バブル期には株式の価格(以下”株価と呼ぶ)”も高値を付け、日本中で取引が活発化します。
しかし、バブル崩壊後には、長期にわたる経済停滞によって、株価は著しく下落してしまいます。
バブル崩壊から20年近くにわたり、低い数値のまま低迷していた日本企業の株価は、2013年にスタートしたアベノミクスによって、ようやく経済成長をしていた時代の高い数値を取り戻すことができました。
その影響で、日本の現状の株式市場は好調に見えるかも知れませんが、今後は人口減少による国内経済の縮小によって、長期的な利益の拡大が望めない企業も多いです。
現在では、株式は証券会社を通じて購入することができまが、どの企業の株式を購入しても利益を出せるという状況ではありません。
なので、日本企業の株式を購入する場合には、どの企業に将来性があるのかを、慎重に見極める必要があります。
まとめ
ここまで、以下の内容をお伝えしました。
- そもそも株式とはなにか?
- 世界の株式の歴史
- 日本の株式の歴史
株式は、発行することで、会社が事業をはじめるために必要な資金を集められ、そして購入者は利益の配当を受けられるという、非常に優れた仕組みです。
株式が存在しなければ、現代の世界が物質的、経済的に高度に発展することはできなかったと言ってよいでしょう。
株式は、一部の大資本家だけが扱うものではなく、証券会社を通じて、私たち一般人が気軽に購入できるものです。
終身雇用や年金の崩壊が現実的な問題となっている現代では、給与をもらう以外で資産形成をするために、株式への投資が有効な手段となっています。
株式への投資は、初心者が無勉強で利益を出せるほどカンタンなものではありません。
当サイト「お金の窓口」で紹介している記事やセミナーで、ぜひ株式への投資方法を学んでみてください!