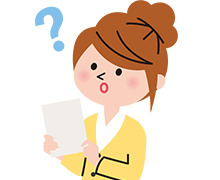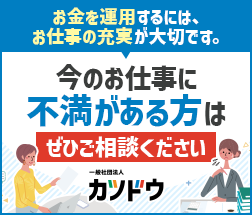「貯蓄から投資」という意識の変化の中、NISAやiDecoなどの投資優遇政策の後押しもあり投資を始める方が増えてきています。
しかし、実際に投資を始めた方でも
「投資を始めてみたものの思ったよりも資産が伸びないなぁ……」
「日本には魅力的な商品って少ないよなぁ……」
と感じている方もいるかと思います。
そんな方には海外投資に目を向けることをおすすめします。特に日本に地理的に近く、世界的な金融センターである香港がその第1の候補です。
この記事では、香港と日本の証券会社を比較して、それぞれの投資環境の違いについて解説します。香港を代表する証券会社としてHSBC香港(*1)とBoom証券(*2)、日本の代表として楽天証券(*3)を事例に挙げます。
*1 HSBC香港・・・イギリスに本社を置くグローバル銀行。時価総額は金融機関の中で世界6位。歴史的な背景から香港にも拠点を置く。香港では銀行と証券会社の垣根がないため、HSBC香港などの銀行口座があれば投資も可能。
*2 Boom証券・・・香港の個人投資家向けのオンライン証券会社。2010年に日本のマネックス証券が買収しMonex Boom証券に社名変更。
*3 楽天証券・・・楽天ポイント投資プログラムや、世界最大級の運用会社バンガード社と提携した新しい投資商品を発売するなど、日本の証券業界をリードする会社。取引手数料はSBI証券と並び業界最低レベル。
この比較を通して、香港で投資することのメリットが数多くあることがわかります。
香港と日本の証券会社で購入できる投資商品の比較
 株式、投資信託、債券の3つのカテゴリーで日本と香港の比較をします。
株式、投資信託、債券の3つのカテゴリーで日本と香港の比較をします。
株式
まず、株式について比べてみましょう。
下の表は各証券会社から取引できる株式市場の一覧です。
| 日本 | 米 | 香港 | 中国A | 中国B | シンガポール | タイ | インドネシア | マレーシア | 豪 | 韓国 | 台湾 | フィリピン | |
| 楽天 | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ 上海のみ |
✅ | ✅ | ✅ | ✅ | |||||
| Boom | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ |
| HSBC | ✅ | ✅ | ✅ |
*データは2019年6月時点
この表で一番目を引くのはBoom証券で取引できる市場の多さです。日米中を初めASEAN諸国や韓国、台湾など、合計で13市場への投資ができます。
日本から投資が難しい国でも、Boom証券を利用すればこれらの市場に簡単にアクセスできます。新興国特有のボラティリティの高さや高配当を狙った投資など、投資の幅を広げてくれます。
また、人気のあるETFですが、Boom証券の取り扱い銘柄数は約1400本である一方で、楽天証券は500本です。圧倒的にBoom証券の方が購入の選択肢が多いことがわかります。
日本では金融庁に登録された銘柄しか取引できませんが、グローバルに開かれた香港の市場では海外のETFがそのまま購入できる点が魅力です。
投資信託
日本で人気のある投資信託ですが、もちろん香港にもあります。
投資信託の品揃えはHSBC香港が強いです。ブラックロックやフィデリティなど世界で一流の資産運用会社の商品が数多く揃っています。
HSBC香港の取り扱い本数は1200種類、楽天は2500種類です。「数」で比べると楽天が倍以上ありますが、「質」で比べると優劣は逆転します。
例えば1年のトータルリターンがマイナスなっている商品の割合を比べてみると、HSBC香港は全体の10%程度である一方、楽天証券は50%近くあり、HSBC香港が収益率の高い商品を数多く取り扱っているかがわかります。
債券
最後に債券について見てみましょう。
現在募集されている新発債の数を見ると、HSBC香港が55本に対して楽天証券は15本です。香港が日本を圧倒しています。
なぜ、そんなに差があるのでしょうか?
その理由は、外国企業が日本で社債を発行する際、目論見書を日本語で作成する手間とコストがかかるからです。そのため外国企業は日本で債券を発行することを敬遠します。
一方で旧イギリス領である香港は英語が公用語のため、外国企業にとって言語の壁がありません。そのため香港には世界中から商品が集まりやすい特徴があります。
例えばIBMやコカコーラなどの安全性の高い米国のグローバル企業の社債を数多く購入できることも香港市場の魅力の一つです。
また、利回りについても香港の方が条件が良いケースもあります。そのことで日本のソフトバンクの社債について有名な話をご紹介します。
2017年、ソフトバンクが日本で発行した円建社債の利率は2%程度でした。その一方、同時期に香港で発行された米ドル建の社債は5%弱でした。
当然、為替などのリスクがあるため利回りに差が出てきます。しかし、利回り3%の差は資産形成に大きなインパクトを与えます。
このように香港は量、質ともに高い債券市場が整っており、投資の幅を広げてくれます。
なお、Boom証券では債券の取り扱いがありません。
香港と日本の証券会社の手数料と税金の比較
 次に、手数料の比較をしていきましょう。ここではどの証券会社でも購入できる米国株を例にとって比較してみました。
次に、手数料の比較をしていきましょう。ここではどの証券会社でも購入できる米国株を例にとって比較してみました。
| 売買手数料 | その他手数料 | 配当源泉税 | |
| 楽天 | 5〜20米ドル(0.45%) 特定口座、一般口座、NISA口座共通 |
売却時 SEC Fee 0.00207% |
日:20.315% 米:10% |
| Boom | 一律20米ドル | 売却時 ・SEC Fee 0.00207% ・Trading fee 0.00119米ドル/株 配当受取時 ・3米ドル/配当 |
香:0% 米:30% |
| HSBC | 一律18米ドル | 売却時 SEC Fee 0.00207% |
香:0% 米:30% |
株式投資の成績は株価の推移だけではなく手数料と税金も重要になります。しっかりと比較して手数料と税金で負けないように投資して行くことが賢明です。
手数料
手数料は各社似ていますが、若干の違いがあります。
3社の比較では以下の結論です。
- 一度の取引が4,000米ドル未満なら楽天証券がお得
- 一度の取引が4,000米ドル以上ならHSBC香港がお得
この点、Boom証券は売買手数料に加え、売却時と配当収入時の手数料が発生するので他者に比べて不利になります。ただし、広くASEAN株に投資できることがBoom証券の強みなので、手数料を意識しながら値上がり益や高配当を狙っていくのも面白いです。
税金
日本では株などを売買した際の利益と配当について約20%の税金がかかりますが、香港では非課税です。香港がタックスヘイブン(租税回避地)と呼ばれる理由です。
しかし、日本の居住者はどの国で発生した所得であろうと日本の税法に従って日本に納税する必要があります。この点、誤解する人が多いので正しく理解しておきましょう。
その上で、条件の良い香港の商品を中心に資産のポートフォリオを築き、NISA(*)などの優遇税制をうまく活用しながら利益を最大化することが大切です。
(*)香港の証券会社で購入した株をNISAとして申告することができませんのでご注意ください。日本国内のNISA口座が必要です。
まとめ
日本の投資信託のうち50%の商品がマイナス運用なのに対してHSBC香港は10%しかないという事例からも分かるように、香港と日本では投資環境が大きく異なります。
日本での投資に限界を感じ、もっと投資に幅を持たせ、高い利回りを狙いたい方は、ぜひ香港に資産運用の拠点を移すことをおすすめします。
香港投資の最初のステップは、HSBC香港やBoom証券などで口座を開設することです。「お金の窓口」では信頼できる口座開設代行業社を紹介することも可能ですので、お気軽にメールかLINEでお問い合わせください。