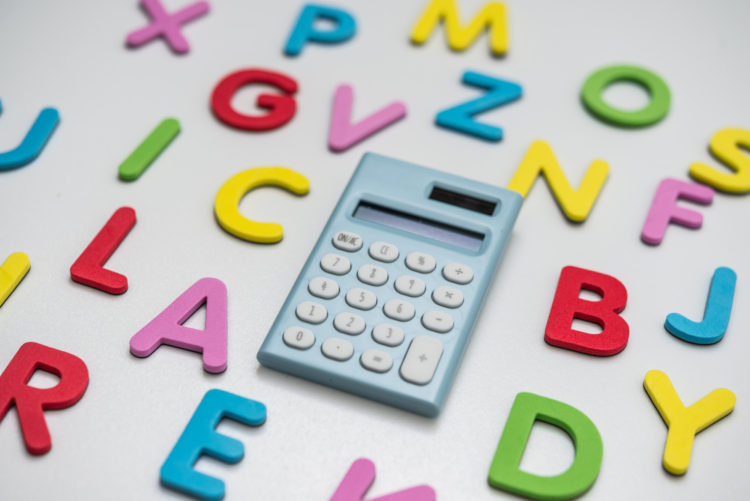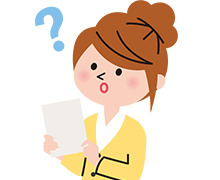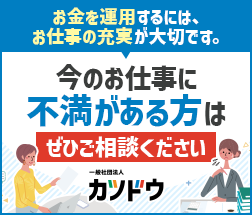介護保険制度は高齢化に伴って重要なものとなっており、家族や自分自身が介護が必要になった時には無くてはならない存在です。
しかし、実際に介護保険料を支払っていても、どのような仕組みで介護保険料が決められているのかは知らないという人が多いでしょう。
自身が利用する可能性もある介護保険だからこそ、仕組みをきちんと理解して介護保険の重要性について再確認しなくてはなりません。
そこで、介護保険料の仕組みや保険料の算出について解説していきます。
介護保険制度の誕生背景
介護保険制度は、社会全体で介護が必要となった高齢者を支えるための制度です。この介護保険制度が誕生したのは2000年ですので、比較的新しい制度になります。
では、どのような背景で介護保険制度が誕生することになったのでしょうか?
介護保険制度が誕生する前まで
介護保険制度が施行される2000年より以前は、各市区町村が主体で社会福祉サービスを提供するものでした。
しかし、これらは措置制度となるので、低所得者や単身の高齢者が対象であり、利用できるサービスやケアも限られていたのです。
そのため、利用したくても該当条件にあたらないケースが多いことや、家族や利用者の意向は汲みこまれることがないことが問題でした。介護は家族が負担するということ以外の選択肢が少ない時代だったのです。
日本の介護に関する課題
日本は世界の中でも長寿国であり、年々介護が必要な高齢者や長期化する介護が問題となってきました。
また、少子高齢化や核家族化、女性の社会進出などの進展に伴い、家族が介護するということが難しい時代になりました。
高齢化によって医療費や介護費が多大となるだけではなく、寝たきりの高齢者の長期入院も問題となり、介護の根本的な見直しが行われるようになったのです。
現在の介護保険制度
介護保険制度が実施されるようになり、介護サービス費用のサポートだけではなく、高齢者が自立した生活をできるようにサポートするサービスも提案しています。
これまで社会福祉法人や医療法人によって運営されていた介護事業に民間企業も参入するようになり、介護サービスの幅が広がると同時に、利用者や家族がサービスを選べるようになったのです。
高齢化はますます進み、介護保険制度はより重要視されるようになってくるでしょう。
介護保険制度は3年ごとの見直しがされるので、社会の実情を汲んだ有益なサービスを要介護者が受けられるように変化し続けます。
介護保険料の財源と仕組み
現在介護保険料は、40歳から支払い義務が生じます。そして、一生涯保険料を支払っていくことになります。
40歳~64歳までは第二号被保険者となり、65歳以上が第一号被保険者という分類に分かれます。
まずは、介護保険がどのような仕組みになっていて、どの財源で補填されているのか見ていきましょう。
介護保険制度の仕組み
介護保険を受けるには、保険料を納付している被保険者が、市区町村に要介護認定を受けて、要支援もしくは要介護に認定される必要があります。
そして、認定されれば自己負担1~3割の支払いで介護サービスを利用できます。そうすると、サービス提供者は市町村区にサービス費用の自己負担以外の費用を請求するのです。
介護保険料の財源
介護保険の被保険者が介護保険サービスを利用する場合、本人の負担は1~3割程度となり、残りは自治体が支払うことになります。
この財源はどのように調達されているのかというと、資金の50%は被保険者が収めている保険料になります。そして、残り50%が公費となり、国が25%と都道府県と市区町村が12.5%ずつ負担しているのです。
保険料の算出方法
介護保険料の50%が被保険者の納付となりますが、どのように保険料を算出しているのかというと、介護サービスに必要な給付額を3年ごとに見直す際に決められます。
その予算の中の50%が被保険者の納める保険料になるのです。ただし、第一号被保険者と第二号被保険者では保険料の支払い方法だけではなく、計算方法まで異なります。
第二号被保険者の保険料算出方法
保険料全体の50%が被保険者の納付になりますが、被保険者が全員同等の金額を納めるわけではありません。
第二号保険者の保険料が27%、第一号保険者の保険料23%となります。
つまり、自身の居住する市区町村が必要とする給付額の予算額の23%もしくは27%を、市区町村に居住する被保険者の総数で割ることで算出されるのです。
ただし、第二号被保険者の場合、まだ現役で働いている人も多いものです。そういった場合には、健康保険と一緒に給料から引かれる形となり、事業主が被保険者と同額負担します。
そのため、算出方法も健康保険等と同様で、4月~6月の給与を平均して標準報酬月額表の等級に当てはめて決められます。この標準報酬月額表は都道府県で異なるだけではなく、それぞれの健康保険組合でも違うので、納付する保険料に差が出るのです。
第一号被保険者の保険料算出方法
65歳以上の第一号被保険者の場合は、収入も考慮した上で、負担が大きくなり過ぎないように所得段階を分けて保険料率を掛け合わせて算出しています。
つまり、介護保険料は、住んでいる市区町村ごとに異なるだけではなく、所得状況によっても異なることになるのです。前年収入状況に基づき、各自治体によって設定された所得段階で個人ごとに算出されます。
所得段階は国の指針では9段階とされていますが、自治体によっては更に細かく区分されています。
例えば、東京の新宿区であれば16段階で分けられ、0.4~3.7倍の料率差があります。一方で、神奈川県の湯河原町であれば10段階で分けられており、0.45~1.9倍の料率差となっています。
このように、住んでいる自治体と収入で異なりますが、公平性は保たれています。
今後の介護保険制度の変化
前述しましたが、介護保険制度は社会情勢などを踏まえた上で更新する必要があるので、3年ごとの見直しが行われます。
2019年現在、次期介護保険法改正は2021年となりますが、今後の日本における介護保険はどのように変化していくことが予想されるのでしょうか?
介護保険財政は厳しくなる?
少子高齢化が進む中で、介護は更に必要性が高まるものの介護保険財政への不安があります。
現役世代である第一号被保険者と、同額負担している企業の負担が大きくなりつつあるため、更なる介護保険財政を支える世代が必要となります。
そこで、今後の展開としては給付の見直しが検討される可能性が高いと言えるでしょう。
介護予防の推進
少子化に伴い、介護保険財政が厳しくなるだけではなく、介護する人材も不足することが予想されます。
そこで、介護予防となる日常生活の支援事業がより一層推進されるようになると考えられます。
国で規定するのではなく、地域に合ったサービスを提案し、地域社会と地域の高齢者が一丸となって支え合える体制を作らなくてはなりません。
そして、出来る限り要介護者を減らすことが目標となるでしょう。
まとめ
今は介護サービスを利用していないとしても、今後家族もしくは自分自身が利用する可能性はゼロではありません。
必要になった時に利用できるように、介護保険制度をきちんと理解しておきましょう。