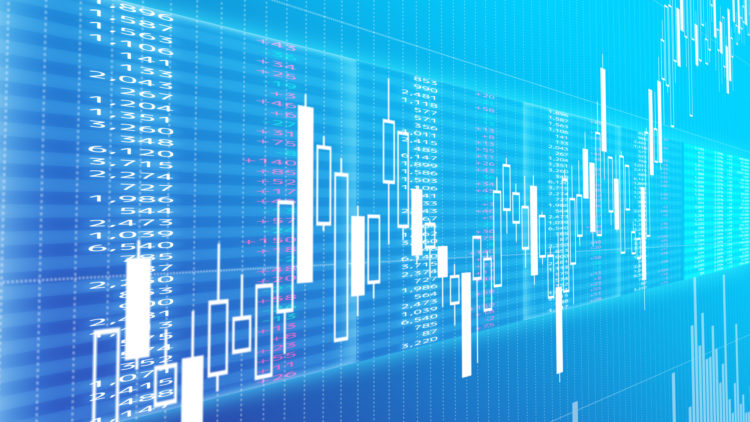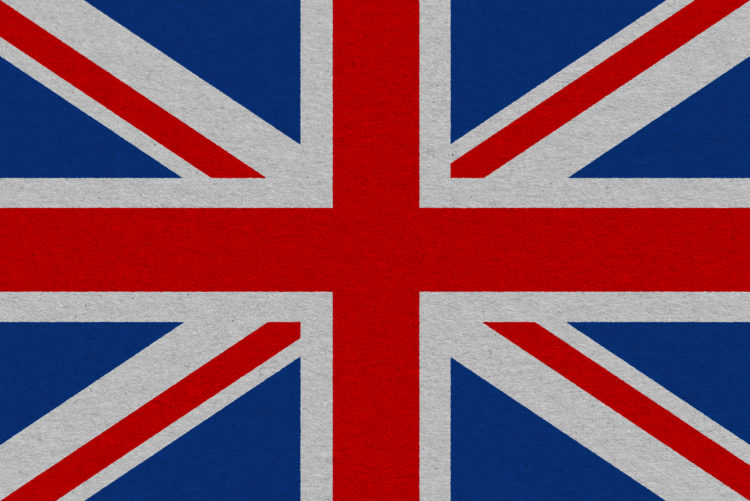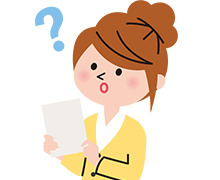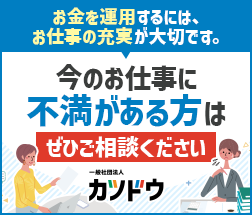2016年にイギリスがEU(European Union:欧州連合)から離脱すること決めた瞬間、世界では激震が走り今後の経済について様々な憶測がなされました。
このイギリスのEUからの離脱は、一般的にブレグジットと呼ばれています。ブレグジットは英語でBrexitと表され、Britain(イギリス)とexit(出る)を合わせて造られた造語です。
ただちに離脱するわけではなく準備期間を経て離脱するため、ブレグジットを起源とした大きな経済危機は生じませんでした。
しかし、ブレグジットにより今後のイギリスやEUの経済あるいは社会構造が変化しているので、特に投資家は注目していく必要があります。
この記事では、ブレグジットのイギリス国内外の主に経済への影響について検証します。
ブレグジット決定の瞬間

2016年の2月、当時のキャメロン首相は国民に約束していた通りに、イギリスのEU離脱を問う国民投票を行うことを宣言しました。
イギリスのEU離脱を問う国民投票の結果は2016年の6月に発表され、残留48%に対して離脱52%という結果になり、イギリスはEUを離脱することを決定しました。
議会がこの決定に従わなければならないという法的拘束力はないのですが、慣習的にあるいは民主主義の手続き上従わなければなりません。
実は、この時筆者はイギリスで働いていました。
イギリス国内でEU懐疑論が活発になっているのを知っていましたが、今回はEU圏内で経済的繁栄の恩恵を受けてきたイギリスが離脱することはないだろうと見ていましたので、非常に驚きました。
それもそのはずで、私が働いていたケンブリッジやロンドンのようなグローバリゼーションの恩恵を受けている都市では、EU残留派が多くを占めていました。
しかし、一方で地方にある多くの貧しい市町村では離脱派が多数を占めていました。
ただし、これはイングランドなどの場合で、イギリス北部地方のスコットランドでのほとんどの都市や市町村では残留派が多数となっていました。
社会科学的に興味深い話題と思い、調べてみたところ離脱派には一定の合理性が見られるということがわかりました。
また、ブレグジットの経済への影響を考察してみたところ、限定的であるという結論に達しました。
経済的あるいは政治的に危機なのは、むしろEUなのかもしれません。
以下に、詳しいことについて述べていきます。
ブレグジットの経緯
まず、ブレグジットの経緯について簡単に説明します。
国民投票
当時の保守党キャメロン首相は、特にイギリス国内で勢力を増しているEU懐疑論者を抑え込みたいなどの理由があり、EU離脱の可否を問う国民投票を行いました。
結果としては僅差で離脱という結果になりました。詳しい投票結果はイギリスBBCのウェブサイトで見ることができます。
イギリスの正式名称はThe United Kingdom of Great Britain and Northern Irelandで、イングランド、北アイルランド、スコットランド、ウェールズで構成されています。
ロンドンなどの主要な都市はイングランドにあります。離脱派が多数を占めたのは、イングランドとウェールズでした。
一方で、北アイルランドとスコットランドでは残留派が多数を占めました。
スコットランドはイングランドと異なり自由競争よりも民主社会主義的な気質を有しています。
イングランドでの結果を詳しくみてみると、日本人にとって馴染みがあるロンドン、オックスフォード、ケンブリッジでは残留派が多かったもののほとんどの地域で離脱派が多数となりました。
離脱派が多数を占めた地域は貧しいところが多く、グローバル化の波から取り残された人達でした。
メイ首相の就任とリスボン第50条の発動
EUから離脱するという国民投票の結果を受けて、キャメロン首相はEUに残留することを訴えていた自分は次の行く末を決めるリーダーとして相応しくないと述べ、辞任しました。
その後、保守党内での党首選挙が行われ、テリーザ・メイ前内務大臣が首相に就任しました。
就任後、彼女は2017年3月29日にリスボン第50条(EUからの離脱の権利や手続きが定められている条約)を発動させ、ブレグジットの手続きを正式に始めました。
与えられた期間は2年間でした。
EU離脱関連法案の議会での度重なる否決
EU離脱関連法案作成にあたって、イギリス政府は、議会で合意を得る前にEUと交渉してどのように離脱を進めるのか決める必要がありました。
難航したのは、EUとの交渉ではなくイギリス議会でのEU離脱関連法案の合意でした。
EUへ譲歩し過ぎであることや保守党が多数派でないことなどの理由から、離脱協定案はイギリス議会(下院)で3回も否決されました。
その間、結局先述した2年間期限内ではEU離脱関連法案の合意を得ることができなかったため、イギリス政府は延長をEUに申請し受諾されました。
メイ首相は2回延長を行いましたが、それでも合意に至ることはありませんでした。
ボリス・ジョンソン氏が首相に就任
抗議の辞任をする大臣が増えると同時に政府をコントロールすることができなくなったメイ首相は、責任を取って辞任しました。
再びの保守党党首選が行われ、ボリス・ジョンソン氏が首相に選出されました。
ジョンソン氏は国民投票の頃からの強硬な離脱派です。
ジョンソン首相は、自身がまとめEU離脱関連法案が議会を通らなければ、議会の合意なしでブレグジットの手続きを始めることを考えていました。
合意なしで離脱を行えば、例えば、EUとの新たな条約が決まるまで貿易が停止してしまい国民生活に悪影響が出てしまいます。
そこで、多くの下院議員はその事態を防ぐため、「合意なき離脱」を阻止するための法案が議会で可決しました。
保守党の歴史的大勝利とEU離脱関連法案の議会による合意
ジョンソン首相がまとめたEU離脱関連法案は、再び議会で否決されました。
結局、再びブレグジット の期限が延期され、ジョンソン首相は解散総選挙を行いました。
選挙結果は2019年12月12日に公表され、ジョンソン首相率いる保守党は歴史的大勝利を収めた一方で、労働党は歴史的惨敗を喫しました。
イギリス国民は離脱プロセスに疲れてしまったというのが、主な理由の一つのようです。
保守党は多数派となったので離脱関連法案は議会で可決され、イギリスは2020年の1月31日にEUから離脱しました。
離脱後から2020年12月31日までは移行期間です。
この間、イギリスはEU圏内にまだ入っているのですが、イギリスとEUの間で新たな貿易協定などの交渉が行われます。
2020年中に全ての交渉を終わらせる予定です。
その移行期間中、イギリスは議員をEU議会に送れないため、イギリスは議会の決定に関わることができません。
そのような理由から、イギリスはEUとの交渉を出来る限り早期に決着させる必要があります。
短期的な視点視点でのブレグジットの経済への影響
ブレグジットが決まった瞬間のマーケットへの影響
ブレグジットは、株式市場や為替市場へ影響を与えました。
基本的に日本はあまり影響を受けませんでしたが、やはり特にイギリスとEUが影響を受けました。
国民投票結果が公表されたのは2019年6月23日でその日は日曜日でした。
6/24以降の動きを見てみると、EUの主要インデックスであるEURO50はそれほど下がらなかったもののもみ合い相場となり、2016年の12月初旬頃から上昇していきました。
一方で、ブレグジットによるイギリス経済の行く末の不透明感に嫌気がさしてイギリスのポンドは売られ、ドル、ユーロや円に対して大幅に下がりました。
同時に、イギリスの代表的なインデックスであるFTSE100も同様に下がりました。
ブレグジット決定後の不透明さは経済に長期的な悪影響を与えると言われていました。
しかし、その後ポンドは一時的に上がり、FTSE100も回復して投票前よりも大幅に上昇しました。
ブレグジットの結果が出てから雰囲気が落ち着いてきたことや世界経済が持ち直してきたことが、大幅に上昇した主な理由と考えられます。
ただし、ブレグジットによるイギリス経済の不透明さはまだ続いているため、ポンドはまだ低い水準のままです。
ブレグジットは第二のリーマンショックの起源にはならなかった
ブレグジットは、リーマンショックなどの大きな金融危機を引き起こすのではないかと言われていました。
しかし、結局そうなりませんでした。
理由は簡単で、ブレグジットはまだ実際行われておらずかつ準備期間が用意されていたからです。
準備期間が用意されていれば、離脱プロセスを少しずつ進めることができ、経済もそれに合わせることが可能です。
他の理由として、恐らくリーマンショックを契機に金融機関の貸し出しなどの規制が強化されており金融危機がやや起こりにくくなっていることが挙げられます。
ちなみに、これは逆に銀行業界を縮小させました。
長期的な視点でのブレグジットの経済への影響

ブレグジットは特にイギリス経済に影響を与える可能性が高いので、イギリス経済への影響について解説します。
ロンドンの金融センターはブレグジット後でも伸びていく
ロンドンの金融センターの規模は世界第2位です。
規制がシンプルであるため、世界中からの資本がここに集中しています。
ロンドンの金融センターが伸びたのは規制緩和だけでなく、EU単一市場への無料アクセスも理由です。
イギリスがEUから離脱すれば、ロンドンの金融機関はそのアクセス権あるいはライセンスを失ってしまいます。
そこで、多くの金融機関は重要な機能をEU加盟国に移してしまうのではないかと言われていました。
その候補地として、パリ、フランクフルト、アムステルダムなどが挙げられていました。
実際に、RBS(Royal Bank of Scotland)と三菱UFJ銀行などは一部をアムステルダムに移行させましたが、重要な機能についてはロンドンに残しておくようです。
他の金融機関についても同様です。
恐らく、ロンドンの金融機関はブレグジット後もヨーロッパでの本部などの重要機能をロンドンから移転させることはないでしょう。
なぜなら、それらの候補地での規制はロンドンより厳しい上に国際共通語である英語を使えない場合(特にパリ)が多いからです。
加えて、後述しますが、ロンドンでは金融以外にもフィンテックなどの優れた情報技術を有するベンチャー企業がたくさん立ち上がっています。
多くの銀行は業績を回復させるために仮想通貨やフィンテックを導入していますが、彼らはロンドンにとどまってフィンテック企業との提携を進めたいと考えているのではないでしょうか。
以上のことから、ロンドンの金融センターにはブレグジット後も世界有数の金融センターの地位は保持されるでしょう。
ロンドンや世界的に有名な都市はブレグジット の影響を受けない
ロンドンやケンブリッジなどの有名な都市は、世界的に有名で世界中から人材が集まっています。
ケンブリッジとオックスフォードには世界大学ランキングベスト5に常に入っている大学を有している上に、多くの優秀な人材を輩出しています。
ロンドンにおいても世界的に有名な大学がありますが、一方でベンチャー企業などへの投資も盛んです。
特に、AIやフィンテックなどの分野において、優秀な人材やベンチャーが多く輩出されています。
例えば、格安の手数料で海外送金サービスを提供するトランスファーワイズ(TransferWise)はロンドンで起業されました。
EU圏以外にも大きなマーケットが世界にあることやそもそもそれらの都市は世界的ブランドとして確立されていることを考えれば、ブレグジットによりEU圏へアクセスしにくくなったとしても、ロンドンのような大きな都市に大きな悪影響を与えることはないでしょう。
ちなみに、AIベンチャーをロンドンで起業した筆者の友人によれば、ブレグジットは彼の仕事に特に大きな影響を与えることはないようです。
イギリスの科学技術分野には悪影響
しかし、ブレグジットは優秀な人材を輩出しているイギリスの科学技術分野にはすでに大きな影響を与え始めています。
博士などの学位を取得するために、他のEU加盟国からイギリスの大学あるいは大学院に入学するケースが多くみられます。
彼らは英国ビザを取得する必要がないので、イギリスに留学しやすいのです。
しかし、ブレグジット決定後、イギリス政府のEU市民の扱いが不透明になったことなどから、EU加盟国から来る学生や研究者の数は大幅に減少しました。
加えて、ブレグジット後、イギリスの研究者はEUからの大きな研究費に申請できる資格がなくなります。
ただでさえ少ない研究費がさらに少なくなってしまい、研究費獲得競争が激しくなるでしょう。
実際に、筆者のいくらかの知り合いの研究者はイギリスから出て別の国で研究をしています。
ただ、理論や情報系の研究についてはお金があまり必要ないので、イギリスの自然科学は全体的にそちらの分野へ偏る可能性があります。
イギリスの地方経済は大打撃を受ける
実は、イギリスの地方は貧しいところが多く、EUからの経済的支援を受けています。
当然ながら、ブレグジット後はその支援は無くなってしまいます。
さらに、ブレグジットの影響で地方にある自動車などの工場を、他のEU加盟国へ移転させるかあるいは閉鎖することが決定されています。
例えば、ウィルトシャー州スウィンドンにあるホンダの自動車工場は、2021年に閉鎖されます。
以上のことから、ブレグジット後イギリスの地方経済は大打撃を受け、大都市と地方との格差はさらに広がってしまうでしょう。
イギリスはなぜブレグジットを選んだのか

そもそもなぜ多くのイギリス国民はブレグジットを選んだのでしょうか?
理由は主に2つありました。
一つは多すぎる移民。
二つ目は主権をEUから取り戻したいというものです。
多すぎる移民の具体的な問題点として、移民に職を奪われたとか犯罪が多くなったなどと主張されていましたが、それを裏付ける統計データは今のところ存在しません。
ただし、二つ目の主権回復に関しては一理あります。
なぜなら、EUは加盟国の一部の民主主義の機能(正確には各国の議会の機能)を停止させて、EU議会などでルールなどを中央集権的に決めるシステムだからです。
例えば、移民の受け入れに関するルールを各国であまり自由に決めることはできません。
そのルールはEU議会で決められ、加盟国はそれに従わなければなりません。
さらに、各国から参加しているEU議会の政治家や官僚の汚職、イギリスの民主主義はドイツやフランスの民主主義とやや異なることなどを加味すると、EUに対して懐疑的に見るイギリス国民が増えるのは当然かもしれません。
このようなEUに対する懐疑的な考え方は欧州懐疑主義(Euroscepticism)と一般的に呼ばれています。
むしろ心配するべきはEUかもしれない
大きな経済規模を有するイギリスを失うEUも、当然ながらブレグジットの影響を受けます。
EUグローバル経済圏の規模は世界第2位で、加盟国はその恩恵を受けてきましたが、実はEUは実験的な政治システムでやはりまだ不安定な面があります。
ヨーロッパへ投資する際は、EUの不安定な面を知っておくと良いかもしれません。
United States of Europeを作りたいEU
EU の歴史は、1952年に発足した欧州石炭鉄鋼共同体から始まり、加盟国を増やし、1992年に欧州連合EUが発足しました。
その後、共通通貨ユーロが導入されると同時に統合を深化させていきました。
例えば、通貨金融政策は欧州中央銀行ECBが行い、ユーロを導入している加盟国は各々の国の事情に合わせた債券発行や通貨流通量の調整などを行うことができません。
どうやらEUは、United States of Europeヨーロッパ合衆国を構築したいと考えているようです。
理想的には、アメリカ合衆国United States of Americaのような国を目指していると考えられます。
アメリカの場合、各々の州は独立して運営されていますが、EUよりも経済格差はない上にほとんどが移民であるということなどから一定の共通価値観を有しています。
そのようなアメリカでさえも、国内の様々な争いを経て統一したアメリカ合衆国を形成することができました。
EUの場合は、後述するように、加盟国間での大きな経済格差や価値観の大きな違いにより、アメリカのような一つの合衆国を形成することは容易ではないでしょう。
EUは域内格差の問題を抱えている
イギリスが離脱した後のEUには、現在27の国が加盟しています。
GDPなどの指標で見た経済規模は国によって非常に違います。
加えて、北側と南側のヨーロッパでは文化や価値観が異なります。
GDPや一人当たりの収入を見てみると、ドイツ、フランスやオランダなどの北ヨーロッパ諸国と比較してスペイン、イタリアやポルトガルなどの南ヨーロッパ諸国はかなり低いです。
東ヨーロッパの国々になると、それらはさらに低いです。
また、南ヨーロッパ諸国の人々は大らかでいい加減な面が結構ある一方で、北ヨーロッパ諸国では細かいことにこだわる傾向が強いことなどから、南北では慣習が異なります。
元々共産圏にあった東ヨーロッパ諸国も、彼らとは異なる思考や慣習を持っています。
こういった国々を、一つのルールでまとめていくのは至難の業ではないでしょうか。
EU圏内で人の行き来は自由です。
したがって、職があり経済が繁栄している国や都市へ人々は移動し、格差はますます拡大してしまいます。
反EU・極右勢力の台頭
近年、EU圏内で、移民が増えたことや経済格差が広がったことなどにより、反EU・極右勢力の勢いが増してきています。
ブレグジットは反EU的な動きであるため、ブレグジットは彼らを勢いづかせました。
印象的であったのは、エマニュエル・マクロン氏が選出された数年前のフランス大統領選でした。
その際、極右政党の党首であるマリーヌ・ル・ペン氏が決選投票に残ったものの最終的には破れてしまいました。
破れはしたものの、多くの人が彼女を支持していたのは事実です。
次の大統領選挙では、彼女が勝利するかもしれません。
ほとんどの加盟国で同じような現象が起こり、ヨーロッパの株式市場にも影響を及ぼしました。
昨年の11月に就任したフォン・デア・ライエン欧州委員長(EUのトップ)は、新しい環境保護に関わる共通のルールを作りEUの統合をさらに深化させたいと考えているようですが、これは極右勢力の反発を招くことになりそうです。
EU離脱プロセス前後のイギリス経済
1月末に、ブレグジット関連法案がイギリスの議会を通過し、イギリスは2020年1月31日に正式にEUから離脱しました。
しかし、その後イギリスはEUや他の国との貿易協定などの交渉を行い、条約などを締結する必要があります。
与党である保守党が議会で過半数を有しているため、基本的にはスムーズに進みそうですが、2020年中に全ての交渉が終わらないかもしれません。
したがって、イギリスの株式市場への影響は少なそうですが、交渉が難航すればFTSE100が大きく下落する可能性があるので注意が必要です。
この不透明感を抜けた時(少なくとも来年以降)に、FTSE100は大きく上昇する可能性があります。
したがって、今のうちにイギリスの株あるいはFTSE100に投資している投資信託を買っておくと良いかもしれません。