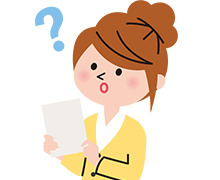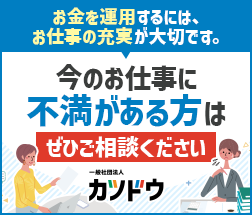中国の通貨である人民元の将来性は高く、中国が米国に次ぐ世界第2位の経済大国であることから、将来は「人民元が国際化してドルに並ぶ基軸通貨になるのでは」と考える人も増えてきています。
しかし、中国の経済力や将来性は大きいものの、金融市場はいまだ閉鎖的で整備されていない一面があります。
人民元が国際化し、より信頼性がある通貨にするためには、中国本土でも変動相場制の撤廃や金利の自由化、資本取引の自由化などを行い、金融面で成長していくことが必要です。
ただ、中国の金融ハブとも言われる香港では、一国二制度に基づく独立した法制度や規制があり、投資家が安心して投資ができる環境が整っています。
中国の金融市場が未発達の現在でも、香港を通して投資資金が流入しているため、中国は急ぐことなく、まわりの環境に合わせて金融市場の自由化を進めていくことができると考えられます。
ここでは、中国人民元が国際化していくための大きな課題である「金融市場の自由化と開放」と、それに必要不可欠な「香港の役割」について詳しく解説していきたいと思いますので、ぜひ参考にしてください。
中国の人民元国際化におけるメリット
 中国の人民元は、現時点では政府がコントロールしており、毎日政府が発表する基準レートをもとに取引されています。
中国の人民元は、現時点では政府がコントロールしており、毎日政府が発表する基準レートをもとに取引されています。
固定相場制ではないけれど変動相場制でもなく、いわば中間の仕組みをとっているといえます。
ただ、中国政府もいずれは変動相場制に移行し、人民元の国際化を進めていきたいと考えています。
なぜなら、人民元が国際化され、中国の経済力を背景に多くの国で使われるような基軸通貨のひとつとなれば、中国や中国の企業にとって大きなメリットがあるからです。
人民元が国際化されることで考えられるメリットにはどのようなものがあるのでしょうか。
為替リスクの軽減
人民元が国際化し、人民元建てで貿易を決済できるようになれば為替変動リスクが少なくなり、先物ヘッジのコストも削減することができます。
例えば、日本の貿易はドル決済で行われていますが、トヨタは1円の円高で400億円の営業利益が減ると言われています。
このように、日本の輸出企業は為替の動きによっては企業業績が悪化し、大きなダメージを受けてしまうこともあります。
これは中国の企業も同じで、ドル決済であれば日本企業と同じように為替変動による影響を受けてしまいます。
しかし、人民元が国際化し、最終的に人民元そのものでの決済ができるようになれば、為替の変動によって企業がダメージを受けることが少なくなり、企業にとってリスクが少なくなるというメリットがあります。
金融における優位性が高まり高収益をあげることができる
人民元が国際通貨、基軸通貨として使われるようになれば、人民元建ての金融商品を世界中の投資家が購入するようになり、中国は欧米の金融機関よりも優位性を保つことができます。
人民元を中心に考えた場合、米国や欧州の金融機関は人民元の為替変動に対してヘッジをかける必要がでてきます。
リスクヘッジにはコストがかかりますし、例えヘッジを行っていたとしても、ヘッジ幅以上の急激な為替変動が起きた場合は大きな損失が出てしまう場合があります。
しかし、中国側は人民元建ての為替商品であれば為替リスクやコストを負う必要がなく、高収益を獲得できるというメリットがあるのです。
現在では、香港と上海が中国の金融都市として発達していますが、人民元建ての金融商品の取引が活発に行われるようになれば、これらの都市が中国の金融センターとしてますます発展していくでしょう。
海外からの投資資金が中国に集まるようになる
人民元が国際化すれば、金融商品を購入するときに人民元とドルの為替レートを気にする必要がなくなります。
人民元が安定した世界の基軸通貨の一つになれば、金融商品で得た人民元をそのまま貿易決済や日々の生活などに使うことができるようになるため、投資家にとってのリスクが少なくなるのです。
例えば、「元圏」と呼ばれる、人民元の一大経済圏ができた場合は、その元圏に所属している国の人は、人民元建ての金融商品に対する為替リスクはなくなることになります。
また、人民元が国際化すれば、人民元に対する不安感が少なくなることから、機関投資家のような大規模な資金が流入する可能性も高くなります。
現在、世界の基軸通貨「ドル」の国であるアメリカは、毎年多額の国債を発行して海外からの資金を集めています。
今後、人民元が国際化し、信用される通貨になれば、中国でも人民元建ての債券や国債を多く発行して世界中から莫大な資金を集めることができるようになります。
国際収支が赤字になってもダメージが少なくなる
人民元が国際化し、多くの国で国際通貨として使われるようになれば、海外の商品やサービスを人民元でそのまま購入できるようになります。
そうなると、たとえ国際収支が赤字になっても自国通貨を増発するだけで、海外の商品を購入・輸入し続けることができます。
中国人民元の国際化によるデメリット
 人民元が国際化され、信頼できる通貨として世界中から取引されることは多くのメリットがありますが、デメリットもあります。
人民元が国際化され、信頼できる通貨として世界中から取引されることは多くのメリットがありますが、デメリットもあります。
それは、国際的なホットマネーの影響を受けやすくなるということです。
金融市場を開放して自由化すると、海外と中国市場がつながるため、資本が自由に移動できるようになります。
その結果、一般投資家はもちろんのこと、多額の資金を動かす海外の機関投資家も人民元や中国の株や債券の売買が自由にできるようになります。
そのため、場合によっては投機的な資金が中国に流入したり、逆に一気に資金を引き上げられて人民元や金融商品の価格が暴落するなどのリスクが発生することになります。
金融市場を開放すると、市場を制御することができないため、このようにコントロールできないことが起こる可能性があります。
それが人民元国際化や金融市場開放におけるデメリットということができるでしょう。
中国の金融市場の現状と問題点
 中国の経済面における発展は目覚ましいものがあり、中国はアメリカに次いでGDPが世界第2位です。
中国の経済面における発展は目覚ましいものがあり、中国はアメリカに次いでGDPが世界第2位です。
そして、中国は3位の日本の2倍以上大差をつけている点も見逃せません。
中国は、このように名実ともに誰もが認める経済大国になりつつあります。
ただ、経済面に比べて金融面の発達が遅れており、それが今後の中国の大きな課題だと言えます。
中国では、金融市場が先進国のように整備されているわけではなく、未熟な点が多くあります。
そのため、今後人民元を国際化していくためには、金融市場を先進国と同じように発展させていく必要があります。
中国の金融市場の問題点はどのようなところにあるのでしょうか。
中国は直接金融が発達していない
中国における間接金融(銀行からの融資)は70%を超えており、中国の企業が資金を調達する場合は、ほぼ銀行の融資に頼っているという現状があります。
先進国であれば、銀行の融資に加えて株式の上場、社債の発行など、様々な資金調達の方法から選ぶことができるため、万が一企業が倒産した場合のリスクも分散されています。
しかし、中国の金融市場はまだ未発達のため、実質銀行からの融資に頼るしか方法がない状態です。
そのため、もしも中国の景気が減速して倒産する企業が増えるようになれば、融資を一手に引き受けている銀行が大きなダメ―ジを受け、それが金融危機のきっかけになってしまう可能性もあります。
中国では、このようなことを防ぐため、間接金融だけではなく、先進国のように直接金融を発展させることが急務といえます。
元安になると資本流出が起こる
政府は直接金融を発展させ、海外から中国への投資を行いやすくするため様々な政策を行ってきました。
その結果、人民元の信頼性や存在感が以前よりも増し、海外の中央銀行や通貨当局が人民元を外貨準備に取り入れるようになりました。
しかし、元安になると問題が発生します。
中国の金融市場は完全に開放されているわけではなく、中国国内・国外の投資家が参入することは簡単ではなく、金融商品も充実していません。
そういったことから、元安が進んでしまった場合は海外からの大きな資金の流入はないにもかかわらず、国内の資産のみが海外に流出してしまうという構造的な問題があるのです。
実際、元安になると貿易決済額や人民元の預金が減少したというデータがあり、人民元安の状態が「資本流出」につながってしまうということを表しています。
| 時期 | 2010年3月 | 2014年12月 | 2017年12月 |
| 人民元預金額 | 708億元 | 1兆36億元 | 5591憶元 |
出典:CEICデータベースよりお金の窓口作成
人民元国際化のために金融市場を開放し、資本取引の自由化に向けて努力していたものの、元安によって「金融システム自由化におけるデメリット」が起きてしまったことになります。
このような事象が起きた場合は、国の資産流出を防ぐために「資本取引の規制」を強めなければならず、人民元国際化の条件である「資本取引の自由化」からは遠ざかってしまうことになります。
今後中国は「人民元国際化のための自由化」と「資本流出のリスク」という相反する二つの事象をどのようにコントロールしていくかが問われていくことになるでしょう。
人民元国際化のために中国が取り組むべき3つの課題
 人民元を国際化し、信頼される通貨として世界で取引されるためには、中国の閉鎖された金融の現状を改善し、先進国と同等のレベルにまで引きあげる必要があります。
人民元を国際化し、信頼される通貨として世界で取引されるためには、中国の閉鎖された金融の現状を改善し、先進国と同等のレベルにまで引きあげる必要があります。
人民元国際化に必要なのは「変動相場制への移行」「金利の自由化」「資本取引の自由化」の3つとされています。
ただ、金融システムが未熟な状態で資本取引の自由化を行うと、中国国内の資産が海外に流出してしまう恐れがあります。
そのため、まずは「変動相場制への移行」と「金利の自由化」を行い、金融システムを整える必要があります。
人民元の変動相場制への移行
人民元の国際化に向けて解決すべき課題として、人民元の変動相場制への移行が挙げられます。
人民元の変動相場制への移行はすでに中国政府としても模索し、取り組んできた課題です。
ただ、急に変動相場制へ移行することは難しいため、今は管理変動相場制となっています。
今の管理変動相場制になったのは2005年で、アメリカから「為替の柔軟性」を求められたことがきっかけです。
アメリカからの要請をうけ、2005年7月に人民元を対ドルレートで2.1%切り上げ、ドルと人民元のレートを固定する「固定相場制」から現在のような「管理変動相場制」に切り替えたという経緯があります。
管理相場制は、毎日為替取引が始まる前に当局が基準値を発表し、その日の人民元の値動きを「基準値の上下一定幅内に規制する」という仕組みです。
現在は変動幅は上下それぞれ2.0%となっています。
最初はこの変動幅はもっと小さく設定されていたのですが、変動相場制への完全移行を念頭に、年々変動幅を広げていっています。
米中貿易摩擦が変動相場制移行の障害に
人民元の国際化のために完全な変動相場制に移行するためには、基準値レートの発表をやめたり、当局の為替介入を控え、誰もが完全に自由な状態で取引ができる環境が必要です。
しかし、米中貿易摩擦などの外的要因が原因で、変動相場制への完全移行はまだ難しいと考えられています。
米国は中国に10%の追加関税をかけることを発表していますが、中国はそれに対抗して人民元を対ドルで安くなるような基準値を発表しています。
人民元を安くすることで、アメリカ国内での販売価格が上がることを防ぎ、貿易への影響を最小限に抑えることができるからです。
このように、中国が人民元のコントロールができる理由は、固定変動相場制だからだといえます。
もしも完全な変動相場制になっていた場合は、米中の貿易摩擦と米国からの高い関税に対して、政府として効果的な対策を行えなかった可能性があります。
米中の貿易摩擦はまだまだ長期化しそうです。このようなことを見ても、完全に変動相場制に移行するにはまだまだ時間がかかるといえるでしょう。
金利の自由化
人民元の国際化には変動相場制の導入に加え、金利の自由化も必要です。
金利を自由化すると金利を高くしたり、低くしたりすることで間接的に金融市場の資金の流れをコントロールすることができるというメリットがあります。
例えば、米国債の利率が大きければその高い利率に魅力を感じ、皆ドルを買ってドル建て米国債を購入する人が多くなります。
その結果、米国は大きな資金を集めることができます。
これと同じように、中国においても金利が自由化して高い金利を設定できるようになると、中国の政府や企業も国内・海外からの多くの投資資金を集めることが可能となります。
このように、金利が自由化すると「金利が資金を誘導する」という機能が強化され、金利政策を有効活用できるようになります。
金利の自由化による他のメリットは以下のようになっています。
資金の利用効率が改善
金利が規制され、低いままの状態だと銀行間に競争が生まれなくなります。
その結果、銀行側としても貸し倒れリスクを防ぐために、「収益も少ないけれど、低リスクの企業」を融資先に選びがちです。
銀行がこのような守りの姿勢に入ると、「まだ実績はないけれども高い将来性を持つ企業」にお金がいきわたらなくなり、その結果、中国国内の高い経済成長がのぞめなくなってきます。
しかし、金利が自由化すると銀行間でも競争が生まれ、借り手のリスクに見合った金利設定ができます。
そのため、「リスクは高いが将来性が高く、高収益を見込める企業」にも融資のお金が循環するようになります。
そうなると企業活動が活発化し、中国の経済成長を後押ししてくれることになります。
また、金利が自由化されると金融商品やサービスが多様化し、魅力的な商品も出てくると予想されます。
現在は高い金利を求めて裏のルートにお金が流れている状態ですが、金利が自由化され魅力的な金融商品に投資ができるようになれば、そのようなこともなくなります。
金利の自由化で中国国内でお金の循環が活発になり、経済にもよい影響を与えるでしょう。
中国の金融市場の開放実現までは香港が存在感を発揮
- 中国単体における経済成長率が少しずつ低下していること
- アメリカとの貿易摩擦が激化していること
などから、まわりの環境が悪化してきているということができます。
そのため、すぐに変動相場制の移行や金利の自由化、資本取引の自由化を行うことは難しいと考えられます。
しかし、これらを実現しなければ、海外投資家が安心して中国に投資を行える環境にはならないでしょう。
人民元は政府が簡単にコントロールすることができますし、所有権などの保証もあいまいなため、最悪の場合は、中国に投資をしてもその資産が凍結されてしまうリスクもあります。
つまり、中国に直接投資を行うには「信頼性」が徹底的に欠けているのです。
しかし、中国には一国二制度をもとに発展している「香港」があります。
香港は中国の金融ハブ都市として発展しており、中国のみならず、経済成長率が高いアジア地域とも近く、どのアジアの全主要都市にも4時間足らずでアクセスできます。
そして、立地の良さと信頼性の高さから8,000社以上が香港を拠点としています。
また、銀行や証券、保険、先物など金融サービスでも健全で透明な規制制度があるなど、中国の都市でありながら独立した法整備や規制がなされていますので、投資家も安心して資金を投入することができます。
つまり、中国に直接投資をすることが不安であっても、香港を通すことで、将来性豊かな中国に対し、低いリスクで安心、安全に投資をすることができるのです。
現在、香港を通して多くの投資家が中国に投資を行っており、その投資資金の恩恵を中国が受けているということになりますので、香港は中国にとってはなくてはならない、重要な都市ということができます。
一国二制度を維持し、海外投資家に信頼性をあたえ、投資を促すことで、中国自体も恩恵を受けられるという仕組みになっているため、香港は金融システムが未熟な中国にとって、手放すことができない重要な存在であるということができるでしょう。
中国の金融市場が将来自由化するまでは時間がかかると考えられるため、それまでは香港が特に大きな存在感を発揮すると期待されています。
中国のバブル崩壊や金融危機を防ぐためにも香港の存在が重要
 中国の経済成長率は高いものの、過去に比べると景気が徐々に減速しており、「バブルが崩壊するのでは?」「金融不安が起こるのではないか」という不安を感じる人が増えてきています。
中国の経済成長率は高いものの、過去に比べると景気が徐々に減速しており、「バブルが崩壊するのでは?」「金融不安が起こるのではないか」という不安を感じる人が増えてきています。
中国は株や債券を使って資金調達をする「直接金融」が発達していないため、ほとんどの企業が銀行融資という「間接金融」に頼っており、その割合が70%以上に達しています。
そのため、景気減速で倒産件数が増えれば、銀行が貸し倒れダメージを一手に受けることになり、多くの不良債権を抱えることになったり、最悪の場合銀行が連鎖倒産してしまう可能性もあります。
このように、中国の景気が減速すれば、間接金融の比重の高さが災いして、中国のバブル崩壊や金融危機のきっかけになる可能性があるのです。
実際、日本のバブル崩壊時には間接金融の割合が66%ほどになっており、バブル崩壊で企業が倒産したダメージを銀行が受け、200兆円以上の不良債権を抱えてしまったという経緯があります。
もちろん銀行だけではどうにもできなかったため、国が介入して約20年かけて返済しましたが、日本にとって長い停滞期が続いてしまうことになりました。
中国の景気減速状況や間接金融割合の多さを見ても、バブル崩壊前の日本と似ているところも多く、景気が一気に悪化する可能性も見えてきています。
ただ、中国には国際的な競争力をもつ「香港」という都市があります。
金融市場が未熟な中国が不安定になればなるほど、成熟した金融サービスを海外の投資家に提供でき、投資資金を呼び込める香港という都市の存在が重要となることは間違いありません。
実際、香港のデモの鎮圧など、当初強い姿勢で望んでいた中国政府ですが、その後は落ち着いています。
夏に公表された中国のGDPの速報値でも予想よりも低い数値であったため、中国の景気減速が明確になってきています。
そのような中、海外投資家に安全な金融市場を提供できる香港をつぶしたり、力を弱めたりすることは中国にとっては得策ではなく、それが逆に中国の金融不安のきっかけにもなりかねないからです。
近年は中国の成長に伴い、上海も金融都市として発展してはいます。
しかし、海外投資家にとっては、一国二制度をもとにした中国とは違う独自の法制度をもち、透明で安心できる取引環境を提供できる香港のほうが信頼性が高いと考えることができます。
香港は、中国の金融市場の自由化を進めたり、中国の景気減速を乗り越えるためになくてはならない都市ということができるでしょう。
中国はいったん停滞期に入る可能性もありますが、香港のサポートを得ながら、金融市場の整備を進めていくことが求められています。
まとめ
中国は経済発展を遂げ、世界第二位の経済大国となっていますが、金融市場はまだ未発達のため、これから乗り越えていかなければならない課題が多くあります。
また、近年は現在は米中貿易摩擦により、アメリカが中国に大きな関税をかけていることから、じわじわと景気が減速してきています。
経済が安定しなければ人民元の国際化を進めることはできないため、この中米の対立をまずは解決しなければならないでしょう。
ただ、中国の人民元国際化における取り組みは少しずつ実を結んできており、2016年には人民元が国際通貨基金(IMF)のSDR構成通貨として組み入れられました。
これは、人民元が通貨として国際的に認められた大きな一歩となっています。
また、香港という国際競争力が高く、信頼性が高い金融サービスを提供できる都市があるというのも中国の強みとなっています。
人民元の国際化の実現までには少し時間がかかるかもしれませんが、今後の動きを注視していきたいですね。