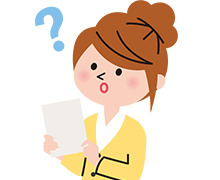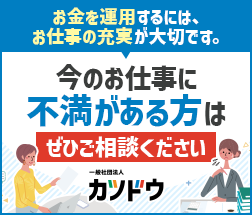中国の通貨である人民元が、ドルや円と同じように自由に取引されるようになることを「人民元の国際化」といいます。
現在は人民元の為替レートは政府がほぼコントロールしており、自由に市場で取引されている他の国の通貨とは事情が異なっています。
しかし、近年は中国の経済発展は目覚ましいことから、近い将来人民元が政府の手を離れて国際化し、ドルやユーロと同じくらい影響力がある通貨になるのではと注目を集めているのです。
人民元が国際化されると、中国と緊密な関係にある国が人民元を機軸通貨として使いはじめる可能性があります。
そうなると「ドル圏」「ユーロ圏」と並び、中国とその周辺国を含めた「元圏」が出現するのではと考えられています。そうなれば、中国の存在感はますます大きくなるでしょう。
中国元が国際化にはいくつか条件があるものの、「中国経済が世界経済において大きな影響を持つようになること」という条件は、すでにクリアしつつあるようにも見えます。
この記事では、人民元が国際化する可能性や課題について詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてください。
中国の人民元が国際化するための条件を解説
 中国は世界において経済力や技術力で他国と圧倒してきています。
中国は世界において経済力や技術力で他国と圧倒してきています。
GDPも米国に次いで世界第二位となっており、名実ともに大国になったと言えるでしょう。
そして、今後は中国の世界経済に与える影響はもちろんのこと、「人民元がいつ国際化するのか」ということに関心が集まってきています。
しかし、中国は経済力は大きくなったものの、まだまだ先進国に比べて遅れている面も多く、課題もあります。
中国の人民元が国際化し、ドルや円などの他の通貨とおなじように自由に取引されるようになるには、以下のような条件をクリアしなければならないとされています。
- 人民元という通貨が信頼されること
- 中国の世界経済におけるシェアが大きくなること(GDPや輸出入)
- 居住者、非居住者どちらも自由に資本取引を行うことができること
(現在は中国国内の富が海外に流出しないよう、資本取引が規制されている) - 中国経済と緊密な国や地域が、ドルではなく人民元に対して為替が安定するような政策をとること
- 中国を中心とした経済圏「元圏」の規模が、ドル圏、ユーロ圏と並んで大きくなること
これらの課題は、大まかにわけて
- 経済面での発展
- 金融システムの自由化や開放
-
の2つに分けることができます。
金融システムの自由化が課題だが人民元の評価は高まっている
 人民元の国際化においては二つの課題がありますが、まだ多くの時間がかかるとされているのは、金融システムの自由化や開放です。
人民元の国際化においては二つの課題がありますが、まだ多くの時間がかかるとされているのは、金融システムの自由化や開放です。
現在、中国の為替レートは実質政府が毎日基準レートを公表し、実質政府のコントロール下にあります。
また、債券や株式市場が発達しておらず、資金調達の方法としては銀行からの融資である「間接金融」が大部分を占めています。
それに加えて資本取引が規制されており、中国で非居住者が自由に金融取引を行うことは難しいことなど、解決しなければならない多くの課題があります。
しかし、中国はすでに世界経済におけるシェアは大きく、世界第二位です。
また、中国経済と緊密な関係をもっている国も多くなってきているため、国際取引による元の取引や使用は中国周辺国ではすすんでいます。
それに加えて、通貨としての存在感も増してきており、2016年10月1日に、IMF(世界通貨基金)のSDR通貨として人民元が採用されました。
また、2017年6月13日は、欧州中央銀行(ECB)は5億ユーロ相当の人民元を外貨準備にはじめて組み入れると発表しています。
このように、世界通貨基金や欧州中央銀行など、世界への影響力が高い機関が人民元を準備通貨として取り入れ始めていることから、人民元の存在感が以前より高まっていることは確かだと言えるでしょう。
中国は世界第二位の経済大国 元が将来国際的な通貨となる可能性は高い
 中国はひと昔前に比べて経済の成長が目覚ましく、現在、中国のGDPはアメリカについて世界第二位となっています。
中国はひと昔前に比べて経済の成長が目覚ましく、現在、中国のGDPはアメリカについて世界第二位となっています。
そして、その規模は3位の日本を大きく引き離し、2倍以上となっています。
中国はすでに世界の中で大きな力を持っていると言えます。
| 順位 | 国名 | 名目GDP(百万ドル単位) |
| 1位 | 米国 | 約18,624,000 |
| 2位 | 中国 | 約11,218,000 |
| 3位 | 日本 | 約4,947,000 |
| 4位 | ドイツ | 約3,477,000 |
| 5位 | イギリス | 約2,647,000 |
出典:総務省統計局 世界の統計2019の第三章 国民経済計算
中国とアジア諸国の関係が緊密化 中国を中心とした経済圏へ
中国とアジア諸国の関係、とりわけASEANやアジアNIEs諸国の動きも注目すべきです。
アジアNIEsは経済成長が著しいアジアの国のことをいい、
- 韓国
- シンガポール
- 台湾
- 香港
のことを指しています。
ASEANは東南アジア諸国連合のことをいい、ASEAN主要6カ国は
- インドネシア
- マレーシア
- フィリピン
- シンガポール
- タイ
- ベトナム
のことをいいます。
近年、東アジアの主要国ともいえるこれらの国々では、対アメリカよりも対中国の貿易額がはるかに多くなってきています。
そして、「アメリカよりも中国を重要視する」という考えのもと、経済や貿易を中国中心に考える国も増えてきています。
実際、これらの国の貿易では、対アメリカ、対日本よりも「対中国」の貿易額が1位となっている国が多く、アジアにおける中国の重要性がますます増してきているといえます。
| タイ | 輸出 | 輸入 |
| 1位 | 中国(12.0%) | 中国(20.1%) |
| 2位 | 米国(11.1%) | 日本(14.2%) |
| 3位 | 日本(9.9%) | 米国(6.0%) |
出典:外務省 タイ王国基礎データ
| シンガポール | 輸出 | 輸入 |
| 1位 | 中国(14.5%) | 中国(13.8%) |
| 2位 | 香港(12.3%) | マレーシア(11.9%) |
| 3位 | マレーシア(10.6%) | 米国(10.5%) |
| インドネシア | 輸出 | 輸入 |
| 1位 | 中国(13.5%) | 中国(23.9%) |
| 2位 | 米国(9.8%) | 日本(9.5%) |
| 3位 | 日本(9.0%) | タイ(5.7%) |
| フィリピン | 輸出 | 輸入 |
| 1位 | 米国(15.6%) | 中国(19.6%) |
| 2位 | 香港(14.2%) | 韓国(10.2%) |
| 3位 | 日本(14.0%) | 日本(9.7%) |
| マレーシア | 輸出 | 輸入 |
| 1位 | シンガポール(14.5%) | 中国(19.6%) |
| 2位 | 中国(13.5%) | シンガポール(11.1%) |
| 3位 | アメリカ(9.5%) | アメリカ(8.8%) |
| ベトナム | 輸出 | 輸入 |
| 1位 | 米国(19.4%) | 中国(27.6%) |
| 2位 | 中国(16.6%) | 韓国(22.1%) |
| 3位 | 日本(7.9%) | 日本(7.9%) |
| 台湾 | 輸出 | 輸入 |
| 1位 | 中国(28.8%) | 中国(18.8%) |
| 2位 | 香港(12.4%) | 日本(15.4%) |
| 3位 | 米国(11.8%) | 米国’12.1%) |
| 韓国 | 輸出 | 輸入 |
| 1位 | 中国(24.8%) | 中国(20.5%) |
| 2位 | 米国(12.0%) | 日本(11.5%) |
| 3位 | ベトナム(8.3%) | 米国(10.6%) |
このように、中国とアジア諸国の結びつきは非常に強くなっており、貿易相手国の上位は中国がほぼ独占している状態となっています。
アジアの成長率予測は世界において群を抜いて高い
 アジア諸国は経済成長率も高いと予想されており、世界においても突出しており、非常にポテンシャルが高い国々であるということができます。
アジア諸国は経済成長率も高いと予想されており、世界においても突出しており、非常にポテンシャルが高い国々であるということができます。
アジア各国の今後の経済成長率の予測は以下のようになっています。
| 国名 | 2019年予測 | 2020年予測 |
| 中国 | 約6.4% | 約6.3% |
| 韓国 | 約2.5% | 約2.3% |
| インドネシア | 約5.4% | 約5.3% |
| マレーシア | 約4.8% | 約4.7% |
| フィリピン | 約6.7% | 約6.8% |
| タイ | 約3.7% | 約3.8% |
| ベトナム | 約6.7% | 約6.7% |
| 台湾 | 約2.2% | 約2.1% |
| 香港 | 約2.7% | 約2.7% |
出典 IMF発表データや各国の統計を基にお金の窓口作成
これらの国の中では、インドネシア、マレーシア、フィリピン、ベトナムのGDP成長率が特に高いと予想されており、これらの国の貿易でも中国が上位を占めています。
また、ASEANやNIEsではありませんが、近年成長著しいミャンマーもGDP成長率が2019年約6.6%、2020年は約6.8%(ASIAN DEVELOPMENT BANKのレポートより)となっています。
そして、ミャンマーの貿易では輸出・輸入ともに中国が第一位となっており、ミャンマーとも密接で良好な関係を築いているといえます。
先進国の経済成長率はアジアに比べて非常に低い
 経済の成長が著しいアジアに対して、世界の主要な国々の経済成長率を見てみると、以下のようになっています。
経済の成長が著しいアジアに対して、世界の主要な国々の経済成長率を見てみると、以下のようになっています。
| 国名 | 2019年予測 | 2020年予測 |
| 米国 | 2.6% | 1.9% |
| 日本 | 0.9% | 0.4% |
| ドイツ | 0.7% | 1.7% |
| フランス | 1.6% | 1.4% |
| イタリア | 0.1% | 0.8% |
| スペイン | 2.3% | 1.9% |
| 英国 | 1.3% | 1.4% |
| 中南米 | 0.6% | 2.3% |
| ロシア | 1.2% | 1.9% |
出典 JETRO作成の「世界および主要国地域の経済成長率」より
先進国とASEAN・NIEs諸国の成長率予測を比べると、アジアの成長率予測がいかに高いかということがわかりますね。
「世界でもとびぬけて成長率が高いアジア諸国の、主要貿易相手国が軒並み中国である」という事実だけを見ても、将来における中国の可能性の大きさがうかがえます。
このようなことを考えると、今後大きな成長が見込まれるアジアと、それらの国と緊密な関係を維持している中国で、人民元を中心とした大きな経済圏「元圏」が生まれる可能性は高いといえるのではないでしょうか。
中国が推し進める一帯一路とは?人民元国際化の突破口となる可能性
 中国はすでにASEANやNIEsと緊密な関係を築いていますが、それに加えて「一帯一路」という政策を推し進めています。
中国はすでにASEANやNIEsと緊密な関係を築いていますが、それに加えて「一帯一路」という政策を推し進めています。
一帯一路とは、「現代版のシルクロード経済圏構想」ともいうことができる計画で、古代シルクロード意識しながらアジアからヨーロッパ、アフリカ大陸にいたる一大経済圏の構築を目指すものです。
一帯一路の具体的な地域は、中国沿岸部から東南アジア、スリランカ、アラビア半島の沿岸部、アフリカ東岸となっています。
そして、これらの地域おいて、今後数十年かけて道路や港湾、パイプライン、通信設備、発電所などのインフラ投資を行い、製造や電子商取引、貿易、金融、テクノロジーなどの産業を活性化していく計画となっています。
一帯一路では、このルート以外にもロシアを経由するルートや東南アジアからパキスタンに至るルート、中国から回路でインドシナ半島へ至るルートなど様々なルートが考えられており、最終的には複数のルートからなる非常に大規模な構想となっています。
非常に大規模なこの一帯一路の地域は、将来世界経済の中心のひとつになる可能性が高いといえるでしょう。
一帯一路は、アジア、中東、欧州、中国の計65か国をカバーしています。
一帯一路に含まれる国の人口や貿易額、GDPは以下のようになっており、一帯一路の国々における今後の将来性は非常に高いと考えることができます。
| 一帯一路の人口 | 一帯一路のGDP |
| 世界の人口の62.7% | 世界の31.2% |
出典:JRIレビュー 一帯一路の進展で変わる中国と沿線諸国との経済関係より
すでにASEANやNIEsと緊密な関係を築いていることに加え、中国は一帯一路の国々にも様々な投資を行い、深いかかわりをもっています。
これらの投資は人民元建てで行われており、一帯一路の国々にも「人民元」が浸透していく仕組みとなっています。
また、一帯一路構想には中国だけではなく、他の先進国も多くの投資を行っており、他の国も「一帯一路構想への投資」に可能性を見出していることから、将来は巨大な経済圏となることが予想できます。
そして、この構想のリーダーシップをとっているのは中国です。
今後、世界におけるこの大きな経済圏の形成には、中国の存在が欠かせなくなっています。
このように、ASEANやNIEs、一帯一路など、今後成長が見込まれる地域には中国が何らかのかたちでかかわっています。
世界で将来性が高い複数の地域や国のすべてと緊密な関係を築いているのは、世界中をみても中国だけと言うことができます。
今後はこのような国と国とのかかわりの中で、人民元が少しずつ浸透していく可能性が高いと考えられます。
世界の基軸通貨の分散化が望まれている
 人民元の国際化は、中国だけの考えではなく、世界の後押しもあります。
人民元の国際化は、中国だけの考えではなく、世界の後押しもあります。
過去のリーマンショックがきっかけとなり「ドルのみが基軸通貨の世界は危険だ」という考えが市場関係者の共通認識となっているのです。
ひとつの通貨に依存していると、何か大きな危機が起こったときに世界中が大混乱に陥ってしまう可能性があります。
そのため、ドル・ユーロ・人民元という「3つの基軸通貨」を持つ世界のほうが、危機が起こってもダメージが少なくなるのではという考えを持つ人も多く存在するのです。
世界各国が中国元の国際化に反対しているのであれば、実現は難しいと言えます。
しかし、リーマンショックをきっかけに「ドル一強」体制に対する懸念が広がっているため、人民元国際化に向けて、追い風が吹いていると考えることができます。
人民元国際化における課題は金融市場の自由化
 今まで説明してきたように、中国は自国の経済力も高く、成長率が高い国々とも貿易や現地への投資などで深く結びついています。
今まで説明してきたように、中国は自国の経済力も高く、成長率が高い国々とも貿易や現地への投資などで深く結びついています。
しかし、アジアや一帯一路の国々は、貿易面では中国と密接なかかわりがあるものの、金融面の結びつきは弱く、それが今後の課題となっています。
中国では人民元が変動制ではなく、政府がコントロールしている状態のため、信頼性が高い通貨ということはできません。
また、中国では金利が自由化されておらず魅力的な金融商品は少なく、また、海外の投資家が自由に金融商品を買える状態ではないことから、海外から中国への投資はまだまだ少ないという現状があります。
中国とアジア各国の結びつきは強いものの、それらの国々は米国債を購入しており、金融面では依然として中国よりアメリカとの結びつきが強くなっている状態です。
今後、中国の金融市場が先進国同様に開放され、人民元の信頼性も高まれば、アジアの国々は中国が発行した国債などの金融商品を買うことが考えられます。
そうなると貿易面だけではなく金融面でも中国とアジアの結びつきが高くなることになります。
そのような段階まで進めば、人民元が世界の基軸通貨の一つとなる実現可能性も高くなりますし、人民元を中心とした「元圏」が成立するのではと考えられます。
中国の景気に翳りが見え始めているのが不安要素
 人民元の国際化には、中国が世界経済において影響力を持つことが不可欠です。
人民元の国際化には、中国が世界経済において影響力を持つことが不可欠です。
ただ、現在世界第二位の経済大国ではあるものの、その推移をみると、中国の勢いは衰えているということができます。
中国の実質経済成長率の推移を見ると、以下のようになっています。
| 年度 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 経済成長率 | 7.8 | 7.3 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 6.5 |
出典 IMFデータよりお金の窓口作成
また、2019年4~6月期の最新の成長率速報値は6.2%となっており、1992年以降最低を記録しています。
このように、中国は世界における経済大国ではあるけれども、中国単体での成長は徐々に低下しており、中国の今後の経済成長にかげりが見え始めているということもできます。
また、米中の貿易摩擦問題も大きくなってきており、解決の糸口が見えていません。
この
成長率が著しいアジアの国々との関係が深いことは中国にとってプラス材料ではありますが、中国と米国の貿易摩擦問題が長引けば、中国の経済が大きなダメージを受けることも考えられます。
中国の経済成長には不安要素も出てきたことが、人民元国際化にとってはマイナス材料であり、今後乗り越えなければならない課題といえるでしょう。
まとめ
中国が世界第二位の経済大国となり、世界経済に大きな影響を持ち始めたことから、人民元が国際化し、「元圏」が成立する可能性がみえつつあります。
もちろん、中国は金融システムがまだ未発達であり、様々な課題があることからすぐに実現するとは言えません。
しかし、中国は様々な国を取り込んで緊密な関係を築いていること、それらの国々の経済成長率が著しいことから、将来「元圏」成立の可能性は十分にあると判断することができます。
ただ、中国としての経済成長にはかげりが見え始めているため、今後中国の経済がどうなっていくのかを慎重に見極める必要があります。
人民元の国際化や元圏が成立すると、世界情勢が大きく変化する可能性がありますので、これからも中国やアジアの動きを注視していきましょう。