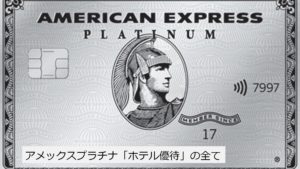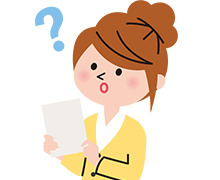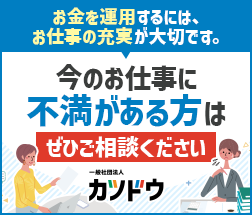みなさんは『人生の三大費用』を知っているでしょうか?
人生の三大費用とは、教育費・住宅の購入費・老後の生活費を指します。この3つの費用は人生において大きなものであり、計画的な準備が大切です。しかし、それぞれの具体的な費用や対策を知ることは簡単ではありません。
今回の記事を通して、人生に大きな影響を与える三大費用についてしっかりと知りましょう。
教育費
子どもにかかる教育費は以下の2つの表を参考にしてください。
〈幼稚園~高校の学習費の総額〉
| 幼稚園 | 小学校 | 中学校 | 高校 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 | 公立 | 私立 |
| 233,947円 | 482,392円 | 322,310円 | 1,528,237円 | 478,554円 | 1,326,933円 | 450,862円 | 1,040,168円 |
(参考:文部科学省 平成28年度子供の学習費調査の公表について)
〈大学生の学費と生活費の合計(1年間)〉
| 事象 | 支出額の総額 |
|---|---|
| 国立(自宅通い) | 1,090,100円 |
| 国立(賃貸) | 1,743,500円 |
| 私立(自宅通い) | 1,759,400円 |
| 私立(賃貸) | 2,492,500円 |
ここでの金額は学校の授業料だけでなく、塾や部活動など学校以外の活動費用も含まれています。よって、子どもの進路が決まれば、上記の表を用いて教育費の総額を求めることが可能です。
必要な教育費は公立と私立のどちらに行くかによって大きく変わります。例えば、小学校の学習費は公立か私立かによって約5倍も差が生まれます。中学校でも約3倍の差です。
このように教育費は子どもの進路が左右するといえます。家庭の状況を考えて、無理のないように進路を決めるべきでしょう。
どうしても教育費が用意できない場合は、『教育ローン』や『奨学金』の利用も選択肢の一つです。しかし、家計の状況や子どもに借金を負わせてしまうリスクをしっかりと考えて利用しましょう。
また、大学では独自の給付型奨学金の制度がある可能性も考えられるので一度、チェックしておくべきです。
大学資金を用意してみる
今回は教育費の中で最も高額になりやすい大学の資金について考えてみます。ここでは国立大学と私立大学の2つのパターンを見ていきましょう。
〈国立大学に4年間通う場合の費用の内訳〉
| 項目 | 金額 |
|---|---|
| 入学料 | 282,000円 |
| 授業料 | 535,800円 |
| 受験料 | 17,000円 |
| 修学費、課外活動費、通学費 | 135,800円 |
| 食費、住居・光熱費 | 553,300円 |
| 保健衛生費、娯楽・し好費、日常費 | 315,900円 |
| 合計 | 6,462,200円 |
(参考:文部科学省 国立大学等の授業料その他の費用に関する省令、日本学生支援機構 平成28年度学生生活調査結果)
〈私立大学に4年間通う場合の費用の内訳〉
| 項目 | 金額 | |
|---|---|---|
| 文系 | 理系 | |
| 入学料 | 231,811円 | 254,941円 |
| 授業料 | 3,124,012円 | 4,407,416円 |
| 施設設備費 | 609,984円 | 736,408円 |
| 修学費、課外活動費、通学費 | 603,600円 | 603,600円 |
| 食費、住居・光熱費 | 1,256,400円 | 1,256,400円 |
| 保健衛生費、娯楽・し好費、日常費 | 1,315,600円 | 1,315,600円 |
| 合計 | 7,141,407円 | 8,574,365円 |
(参考:文部科学省 平成29年度 私立大学入学者に係る初年度学生納付金 平均額(定員1人当たり)の調査結果について、日本学生支援機構 平成28年度学生生活調査結果)
データを基に大学の費用を計算すると上記のようになります。その他にも、各種保険や教科書代など人によって様々な費用が必要です。
教育費は子どもが生まれてから貯蓄すれば18年間という長さがあります。よって、金融商品を購入して運用すれば、低金利の預金より効率良く貯蓄できるでしょう。
また、子どもが生まれる前から貯蓄できれば、さらに家計の負担を少なくできます。できれば早い段階から貯蓄を始めましょう。
住宅の購入費
住宅の購入は一度で数千万円以上もかかるため、「人生で一番大きな買い物」と言われています。そんな住宅の購入には一体いくらかかるのでしょうか。
住宅の購入費は『物件価格+諸経費』で決まります。そのお金は住宅ローンを組んで購入することが一般的です。
その時の頭金の目安は物件価格の20~30%といわれています。現在では頭金がなくても諸経費を含めて全てローンを組める場合があります。しかし、総返済額が大きくなるので注意が必要です。
ここでは物件価格と諸経費を分けて詳しく解説していきましょう。
物件価格
物件価格は地域や物件の形態によって大きく異なります。ここでは東京23区・首都圏・近畿圏・北海道に分けて説明しましょう。
東京23区・首都圏・近畿圏・北海道の4つに分けた物件区分別の価格は以下の通りです。
| 項目 | 東京23区 | 首都圏 | 近畿圏 | 北海道 |
|---|---|---|---|---|
| 中古マンション | 4,479万円 | 3,333万円 | 2,294万円 | 1,878万円 |
| 中古戸建 | 5,592万円 | 3,142万円 | 1,921万円 | 1,951万円 |
| 新築戸建 | 5,024万円 | 3,468万円 | 2,726万円 | 3,024万円 |
(参考:東日本不動産流通機構 首都圏不動産流通市場の動向(2018年)、近畿圏不動産流通機構 市況トレンド 2019 年 4~6 月期の近畿圏市場、近畿圏不動産流通機構 2017年度年刊市況レポート、不動産流通推進センタ࣮ー 不動産業統計集 3不動産流通、アットホーム)
上記の表から、東京23区に近づくほど物件価格が全体的に上がることが分かります。北海道と東京23区の中古戸建を比べると約3倍の差があるため、地域選びは物件価格に大きな影響があるのです。
地域の中でも物件価格には差が生じています。例えば、2017年の近畿圏内でも大阪市の中古戸建の価格が1,882万円であるの対して、過疎地域の奈良県三宅町では329万円です。
このように地域をより細かく調べると物件価格の相場は異なります。物件を選ぶ時は都道府県単位ではなく、市区町村単位で価格を調べるとよいでしょう。
また、今のところ物件価格の推移は比較的横ばいですが、全体的に緩やかな上昇をしています。将来の購入費を考える場合は少し上乗せして考えておくとよいでしょう。
諸経費
諸経費の目安は新築で物件価格の3~7%、中古で物件価格の6~10%といわれています。中古物件は仲介手数料がかかるため、新築物件と比べて高くなっているようです。
そんな諸経費の内訳は主に以下のようなものがあります。
- 印紙税…課税文書にかかる税金。
- 登録免許税…登記手続きの時にかかる税金。
- 不動産取得税…土地や建物を購入した時にかかる税金。
- 司法書士費用…登記を依頼する費用。
- ローン借入費用…住宅ローンを組む時に金融機関に支払う手数料。
- 火災保険料…建物にかける火災保険の保険料。
上記以外にも、マンションを購入した場合に必要な修繕積立金や中古物件を購入した場合に必要な仲介手数料などがあります。
住宅の購入費を考える時はこういった諸経費も忘れずに計算に入れておきましょう。
買うとしたら、いつ購入するべきか
住宅の購入時期を考える場合は次の点をよく検討しましょう。
- 現在の年齢…若いほど返済が早く終わる。
- 金利…低いほど返済が楽になる。
- 不動産価格…安いほど家計の負担が少なくなる。
実際、いつ購入するべきかという問題は人それぞれとしか答えることができません。
自分たちの年齢や生活状況で組めるローンも変わります。金利や不動産価格も時と共に変化するものです。無理のない範囲で住みたい物件を購入できるなら、その時が最もよいでしょう。
ちなみに、住宅金融支援機構 の『2018年度フラット35利用者調査』によると、住宅の購入は40歳前後が平均です。一つの目安として使ってみてはいかがでしょうか。
また、住宅の購入費を資産運用で貯める時はあまりリスクの高い金融商品を選ばないようにしましょう。もし購入直前に価格が落ちてしまうと、購入予定がずれてしまう可能性があります。
老後の生活費
近年、老後2,000万円問題が人々の注目を浴びました。しかし、老後の生活費は実際どのくらいかかるのでしょうか。
生命保険文化センターの『平成28年度生活保障に関する調査』によると、老後の夫婦2人で最低限必要な生活費は月22万円、ゆとりある生活をするには月に約35万円かかるとされています。
また、総務省の『家計調査報告年報(家計収支編)平成29年』によると、実際の高齢無職世帯の支出平均は月に約24万円です。すでに最低限必要な生活費の水準に近づいていることが分かります。
次に、老後に必要な資産の目安を計算していきましょう。
生命保険文化センターの『平成28年度生活保障に関する調査』によると、老後資金を使い始める年齢は65歳からです。そして、厚生労働省の『平成29年簡易生命表の概況』によると、男子の平均寿命は約81年、女子の平均寿命は約87年となっています。
ここで男女の平均寿命を85歳までと仮定すると、65歳から85歳の20年間の生活費が必要な老後資金の目安といえます。
つまり、平均的な暮らしをするなら24万円×12ヶ月×20年間で約5,700万円、ゆとりある暮らしをするなら約35万円×12ヶ月×20年間で約8,400万円が必要になります。
老後で不足すると考えられる金額
公的年金や退職金などがあるため、老後に必要な金額がそのまま不足するわけではありません。
実際に不足金額を計算してみると、それぞれの生活水準によって約1,000〜6,600万円という範囲で大きく異なります。老後2,000万円問題は誰にでも当てはまるわけではないことがここで分かりました。
老後の不足金額については以下の記事を参考にしてみてください。
ただし、老後の準備を考える必要性は誰にでも共通しています。今後、年金受給額の減額もおおいに考えられるので、今の段階から自助努力が大切です。
加えて、できるだけ早い段階から貯め始めれば、それだけ負担が少なく貯めていけます。老後まで長い期間がある人なら、積極的な投資をして資産運用を検討するべきでしょう。
人生の三大費用を把握して、今すぐ対策しよう
ここまで人生の三大費用について解説してきました。どれも必要な金額が高額で早い段階から計画を立てることが重要です。
また、お金が必要な時期と金額が分かったら、それに向けて資産運用も検討するとよいでしょう。低金利の預金と比べて、効率良く貯蓄できます。
人生の三大費用や資産運用のことなど、お金に関する知識は誰にとっても大切です。このお金の窓口ではそういった情報をたくさん提供しているので、何かあればぜひ相談してください。