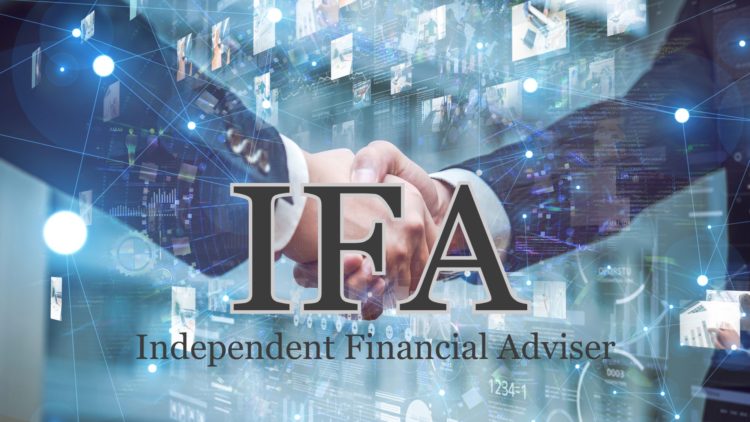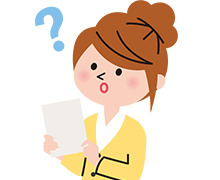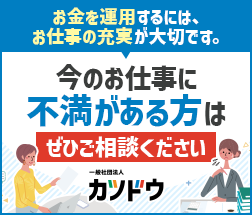香港が投資家にとってベストな選択肢であると聞いても、これまで投資先を国内に限定されていた投資家の方には、いまいちピンと来ないかもしれません。
また、既に香港で投資をしている方や、香港が投資の拠点として良いという認識を持っている方であっても、ところどころの知識が曖昧になっていることが多いです。
投資の世界ではリスクが付き物ですから、香港であっても日本であっても、やり方を間違うと投資資金を失ってしまうことになります。
香港で本格的な投資を始める前に、まずは基礎知識を身につけましょう。
どうして香港で投資をするべきなのか、香港投資のメリットとデメリット、日本やシンガポールとの投資環境の比較、香港で扱われる投資商品、さらには実際に香港で投資を始めるための流れに至るまで、香港投資で失敗しないために必要な情報を完全網羅して、じっくり丁寧にわかりやすく解説します。
香港の投資に必要な全ての情報を盛り込んだため、かなりボリュームがある長文コンテンツになっています。疲れた時には休憩をとりながら、ゆっくりと最後まで読み進めてください。
本文を読み終えるころには、香港での投資を始めるため知識が身につき、すぐにでも香港で投資が始められる準備が整います。
- 香港が投資の拠点に活用され続ける理由をくわしく解説!
- こんなに違う!日本と香港の投資環境の違いとは?
- シンガポールと比べて実感!香港の投資環境の良さとは?
- 投資家を優遇する香港のタックスヘイブン税制とは?
- 香港で取引されている主な金融商品の一覧!
- 香港の投資に用意するべき理想的な金額とは?
- 香港投資で登場する主な金融プレイヤーの一覧!
- 香港投資のワンストップサービス、独立系金融アドバイザー(IFA)とは?
- 香港での投資の最初から最後までの全ステップとは?
- 香港での投資効率を最大化する再投資の方法
- 損しないために知っておきたい手数料の基礎知識とは?
- 現実の利益はどれくらい?香港の長期投資シミュレーション
- 香港の投資まとめ
香港が投資の拠点に活用され続ける理由をくわしく解説!
香港はアジアを代表する投資の拠点(金融センター)のひとつで、世界中から莫大な金融マネーが集まっています。どうして香港が何十年にもわたって、世界の投資家たちに活用され続けているのでしょうか。
香港は、アヘン戦争後の南京条約(1842年)でイギリス領となったことをキッカケに貿易と金融・投資の拠点となりました。世界の名だたる商人たちが香港に拠点を構え、本国から遠く離れた香港の自由なビジネス環境と法規制のもとで、貿易や投資に最適な場所を作り上げていったのです。
アヘン戦争とは、中国からのお茶の輸入が増えたことで貿易赤字に陥ったイギリスが、中国に対して強引にアヘンの輸出を行おうとしたことによって起こった戦争です。南京条約によって香港が割譲されたほか、上海など5つの港が外国に対して開港されました。
香港返還(1997年)によって再び中国の領土となりましたが、現在でも世界の投資家たちに活用され続けています。
このような香港の歴史的な背景を踏まえたうえで、どうして世界の投資家たちが香港を選ぶのか、その理由についてメリットとデメリットを踏まえながら詳しく解説します。
香港のメリット:海外の国や企業、金融商品への投資アクセスが容易!
香港を投資の拠点とするメリットは、投資対象となる金融商品の豊富さと、バラエティ溢れる金融商品を活かすための投資環境の充実度です。
日本を含む多くの国々では規制されてしまっている金融商品であっても香港では個人投資家向けに販売されています。
また、金融商品を評価したり、金融商品の組み合わせをアドバイスしたり、実際に運用を手助けしたり、個人投資家をサポートする役割を担う企業やサービスも整っています。
まずは香港が投資家に選ばれ続ける理由として、香港投資の3つのメリットをご紹介します。
主要産業は金融!投資商品のラインナップが豊富
総面積1,106平方キロメートルの香港は、東京の23区の2倍程度、沖縄本島と同じくらいの大きさしかありません。
こんな香港の主要産業は金融です。世界でも圧倒的に競争力の高い金融サービスを提供することで、香港経済は成り立っています。
のちほど詳しく解説しますが、香港では株式やFXなどの金融商品に加えて、投資信託(ファンド)や生命保険、社債や国債などの豊富な投資商品のラインナップが魅力的です。
もちろん、すべての金融商品に対して一般投資家が投資できるわけではありませんが、ありとあらゆる投資対象がある香港を活用することで、選択肢が広がることは間違いありません。
世界の国や企業へ投資する金融ハブ
世界的にも有数の金融センターである香港では、世界のさまざまな国や企業への投資ができます。香港での投資は、香港の中にある企業だけに投資するということではありません。
アメリカや南米、ヨーロッパ、中国本土、インドやアジア諸国、さらにはアフリカに至るまで、香港を拠点として世界中に投資ができることから、金融ハブとしての役割を担っています。
世界中から香港に集まったお金は、ふたたび世界中へと投資されていくのです。
日本国内への投資が中心である日本と比較すると、金融商品のラインナップの豊富さも相まって香港で取り扱われている金融商品は無数にあり、さまざまな需要を持つ世界の投資家たちに対して最適な金融商品が提供できるのです。
無数に存在する香港の投資商品に関する豊富な知識を持ち、投資家に対して資産運用サービスを提供する独立系金融アドバイザー(IFA)の存在も忘れてはいけません。
香港の投資ではIFAが不可欠ですので、のちほどしっかりと解説させていただきます。
日本から最も近いタックスヘイブン
私たち日本人にとっては、香港を選ぶべき最大のメリットはアクセスの利便性の良さです。
成田から香港への直行便は1日12便、羽田からは1日7便、関空から12便、名古屋(セントレア)から4便で、飛行時間は4時間から5時間程度です。
世界のタックスヘイブンと呼ばれる国や地域の多くが中南米や地中海に集中しており、日本からのアクセスに丸1日を要することと比較すると、香港は日本から極めて近い距離にあります。
香港での投資を始めるにあたっては必ず一度は現地へ行く必要があります。
日常生活で銀行の窓口に行く機会は年間に数回あるかないかであるのと同じように、香港の銀行などの金融機関に直接出向くことは珍しいですが、やはり近いことに越したことはありません。
デメリット:英語が不安!中国のカントリーリスクは大丈夫?
香港が投資に特化した素晴らしい環境を整えているといっても、やはり当然のことながらデメリットもあります。投資にはリターンに伴うリスクがあるように、メリットに対してデメリットがあるものです。
香港が日本から飛行機で5時間程度のアクセスのしやすい立地にあるとは言え、外国であることに違いはありませんので日本語でサービスを受けることはできません。また、投資にあたっては日本円ではなく米ドル建てが基本となりますので為替リスクがあります。
さらに日本でも大きく報じられている通り、2019年夏ごろからの大規模デモの影響が香港の金融街に及ぼす影響についても、投資家としては十分に考慮しておくべきでしょう。
メリットだけを伝えるのではなく、デメリットについても詳しく解説します。
投資の世界の公用語は英語
およそ1世紀半もの間、イギリスの植民地だった香港では公用語が英語です。もちろん中国語も公用語ですが、金融や投資に関わる香港人は英語での会話を好みます。さらに世界の金融センターであるイギリスのシティや、アメリカのニューヨークが英語圏ですので、投資の世界の公用語は英語です。
日本人は英語が苦手な方が多く、金融や投資の専門用語となると英語で理解することが難しいと感じる方も多いでしょう。
最近では日系の金融機関であるNWBが香港に設立され、日本語対応での投資が可能になりましたが、やはり基本的には英語でのやりとりが必要であることが香港を含め海外オフショアでの投資を行うことのデメリットであると言えます。
世界の金融商品の解説を日本語に翻訳するコストは想像以上に高いものであるため、日本で販売されている投資商品の利回りを著しく下げる原因になっています。
香港のように日本人の投資家へのサポートが手厚い場所であれば、英語環境に飛び込んでいくことで有利な投資を行うことが可能になるのです。
米ドル建てで運用する為替リスク
香港の公用語が英語であるのと同じように、香港の投資では米ドル建てが基本となります。
日本円と米ドルの通貨ペアは超長期のボックス相場であるため、米ドル建てのリスクに無関心な投資家も多いのですが、やはり香港での投資には為替リスクがあります。
海外旅行で数日間だけ滞在するのであれば為替の変動の影響は微々たるものですが、投資では扱う金額が大きくなりますので、為替リスクには十分に注意するべきです。
投資ではリスクとリターンが釣り合いますので、為替の変動によって得をすることも多々あります。円高のタイミングを狙うなどの投資戦略が必要になります。
過去10年のドル円相場を平均すると100円前後で推移しており、現在の1ドル109円の相場と比較すると為替によって大きな利益が出る相場であったことが分かります。
反中感情が高まる香港のカントリーリスク
2019年の香港は大規模デモが過激化するなど、投資家にとってネガティブな話題が多い年となりました。
これまで自由な市場と投資環境を提供してきた香港ですが、中国への返還から20年が経ち、カントリーリスクを警戒しなければならない状況となっています。
カントリーリスクとは、特定の国や地域ごとに発生する固有のリスクのことで、主に政治や経済によって発生する相場の変動のことを指します。
長期投資が基本となる香港では、カントリーリスクについても長期の視点でみることが重要です。
香港のリスクについて判断する材料としては、香港の株価を指数化しているMSCI香港指数をチェックしてください。ニュース映像のような過激さを強調する材料ではなく、世界の投資家たちが見る香港の評価が見てとれます。
香港を投資の拠点とする場合であっても、あくまで投資を行うのは世界の投資商品です。
具体的にはアメリカの株式や債券、投資信託などを購入するなど香港以外への投資になります。香港で投資をするからと言って、香港や中国の投資信託を購入する機会は稀ですので、誤解のないようにしてください。
こんなに違う!日本と香港の投資環境の違いとは?
香港で投資をするメリットとデメリットを確認したところで、日本と香港の投資環境の違いについて解説します。
デメリットとして挙げた言葉の壁の問題や為替リスクは、日本国内で投資をすれば発生しない問題ですから、日本国内で投資を行うことにも十分なメリットがあります。
香港の投資を推奨するブログや書籍では、香港を高めようと極端に日本の投資環境を低く評価するものが目立ちますので、よりフラットな視点で日本と香港の投資環境の違いについて解説します。
長期投資に最適化した香港、長期投資に不向きな日本
日本と香港では投資スタンスに大きな違いがあります。
まず香港の投資は、複利の効果を最大限に活用するために長期投資を前提に金融商品が作られていることが多いです。
これは香港に限らず世界的な傾向ですが、短くても5年以上、長期では30年を超える運用を想定した金融商品の設計が行われています。
一方の日本では、投資信託でテーマ型や毎月分配型が主流であることからも分かる通り、短期のトレンドを追いかけたり、短期で収益が得られる金融商品が多いです。
テーマ型投資信託とは、事前に設定された特定のテーマに沿って組み込み銘柄を決定する投資信託のことで、企業の業種や業歴、株価インデックスなどがテーマとして設定されます。ひとつのテーマが長期のトレンドとなることは珍しいため、短期の運用となるケースが多いです。
日本の金融庁が2017年に招集した「家計の安定的な資産形成に関する有識者会議」の報告書には、日本の投資商品が長期運用に不向きであることを明確に記載されています。
ただし、日本の投資商品には一般投資家であっても投資判断が容易で、投資のハードルの低いものが多いことにも言及していますので、一概に日本の投資商品が見劣りするものではありません。
投資家が儲かる香港、金融機関が儲ける日本
日本と香港では、金融機関の収益構造にも大きな違いがあります。
香港の金融機関では、ノーロードと呼ばれる手数料が発生しない投資商品が数多くあります。
手数料が収入の源泉である日本の金融機関での取引に慣れていると、一体どのように香港の金融機関は儲けているのかと不思議に思うかもしれません。
じつは香港の投資商品は、投資家への販売による手数料収入ではなく、運用した利益によって収入を得ているのです。
結果的には日本も香港も投資家の資金から収入を得ていることには違いはありませんが、投資家が儲かることを前提に収益を得る香港と、まず金融機関が儲ける日本には大きな違いがあります。
経済が衰退し続ける日本のカントリーリスク
アベノミクスによって経済が上向く傾向にある日本ですが、長期的には人口減少と共に経済が衰退することが明らかです。
香港のカントリーリスクについては既に解説しましたが、長期的な視点で見ると、日本にもカントリーリスクがあることが分かります。
GDPが世界第3位でありながら世界から日本への金融マネーが集まらない背景には、金融に対する規制の厳しさだけでなく、日本が投資先として魅力的ではないことが挙げられます。
香港の投資では言葉の壁や為替リスクが生じますが、長期的なカントリーリスクという観点で見れば、日本の方がリスクが高いという考えが一般的です。
シンガポールと比べて実感!香港の投資環境の良さとは?
アジアの金融センターとして香港と同じく忘れてはならないのが、シンガポールです。
世界のさまざまな金融商品を取り合うことや、投資家に優しいタックスヘイブン税制を採用していることなど、香港とシンガポールの共通点は多いです。
香港とシンガポールを比較すると、ほぼ同じ条件であるためシンガポールを選択する投資家もいますが、現地を訪れると意外にも苦労が多いです。
両者の比較で決定的な違いとなるのは、シンガポールが世界から「移民」を集めようとしているのに対して、香港は世界から「お金」を集めようとしているという点です。
つまり、シンガポールでは居住者にとってはハイクオリティな投資環境が整っていますが、非居住者には厳しく、銀行口座を開設することさえ容易ではありません。
投資ができる金融商品や税制などの諸条件だけを見比べても知ることのできない決定的な差が、香港とシンガポールにはあります。
投資家を優遇する香港のタックスヘイブン税制とは?
日本では、仮想通貨や不動産などの特別に税率が高い投資を除いても、多くの投資で所得税の最高税率が20%を超えます。
香港のタックスヘイブン税制では、キャピタルゲインが非課税、配当所得が非課税、香港外の源泉所得が非課税など、投資家にメリットのある非課税のオンパレードです。
しかし、実は日本人である私たちの多くは、タックスヘイブンとしての香港の恩恵を受けることは稀(まれ)です。
日本では極端に税率の低い国々での所得に対してタックスヘイブン対策税制が適用されるため、香港では非課税であっても、日本での課税義務が生じるのです。
香港をはじめとした税率の低いアジア諸国への資産回避を防ぐ目的で、2010年に抜本改正された税制の総称です。日本の国税庁では日本人や日本法人の海外資産の監視を強化しており、多額の追徴課税を求められるケースが目立っています。
このため、日本人に対して安易にタックスヘイブンの節税商品を薦める金融業者は、日本の税制への理解が不十分である可能性が高いので注意しましょう。
日本人にとってはあまり恩恵がありませんが、タックスヘイブンならではの香港の投資商品を2つ、ご紹介します。
香港の投資で”保険”商品の人気が高い理由
日本でもお馴染みの「生命保険」は、香港では投資商品として人気が高いです。
いわゆる長期の貯蓄型生命保険と呼ばれる商品で、元本が保証されており、毎月一定額を積み立て続けることで運用金額を増やします。
死亡保障が極めて低利率に設定されているものや、最低利回りが設定されているものなど、香港では投資対象として生命保険が販売されているのです。
貯蓄型生命保険は、香港だけでなくシンガポールでも人気の高い投資商品です。
富裕層たちが”共同名義”の口座を好む理由
日本の銀行口座は、1口座1名義のルールがありますが、香港の銀行では1口座に対して複数名義を設定することができます。
残高確認や引き出しなどの権限を複数名が持つことはリスクとなる一方で、共同名義人のどちらかが死亡した場合でも相続税や贈与税の納税義務が生じないという効果があります。
このような銀行の共同名義制度は、香港以外の国でも認められているケースがあります。
タックスヘイブンである香港では所得の多くが非課税であるため、これらの金融商品が課税逃れの違法行為とならないことから、自由度の高い金融商品が設計・販売されています。
香港で取引されている主な金融商品の一覧!
香港で一般的に取引されている金融商品には次のようなものがあります。海外での投資といえども、日本でも馴染みのある商品が多いです。それぞれの金融商品の香港での特徴と、最近のトレンドについてご紹介します。
株式
香港で投資を行う場合においても、企業の個別株を投資対象とする方は数多くいます。香港からは世界中のさまざまな証券取引所にアクセスできますので、投資の選択肢が飛躍的に増加します。これまではアメリカなどの諸外国の株式が人気でしたが、中国の急成長によって中国国内市場への投資熱も高まっています。
新規上場株式(IPO)
IPO投資では、株式と同じく世界の証券取引所に上場予定の企業のオファーに対して投資を行うことができます。ハイリスクハイリターンな投資ですが、IPO投資に強みを持った金融アドバイザーも香港には数多くいます。
投資信託(ファンド)
日本人にとっては最も馴染みが深く、投資しやすいのが投資信託です。長期の投資商品が多いため複利の効果を活かしやすく、ドルコスト平均法によって為替リスクを軽減することも可能です。日本の投資信託と比較して利回りが高くないものであっても、自動再投資を行うことで高いパフォーマンスが期待できます。
生命保険
香港の税制などを最大限に活用したのが投資商品としての生命保険です。世界の富豪たちから一般投資家に至るまで、生命保険への投資はとても人気が高いです。死亡時に適用される保険としても機能しますが、基本的には存命中に満期を迎えることが前提となっています。
国債・社債
債券投資は利益予想が容易で、レーティング会社による評価によって投資判断が行いやすい投資商品です。積極投資が主流であるイメージの香港ですが、国債や社債への投資も比較的人気が高いです。長期的な投資を行うことが前提の香港では、ハイリスクハイリターンな長期債券も積極的に取り扱いされています。
香港の投資に用意するべき理想的な金額とは?
香港などのタックスヘイブンでの投資といえば、大富豪や資産家が行うものというイメージが強いですが、投資をはじめるだけの資金的な余裕がある方であれば、決してハードルは高いものではありません。
金融商品ごとに異なる香港の最低投資金額
一気に巨額の資金を投じることも投資のひとつですが、日本国内で販売されている金融商品と同じく毎月コツコツと積み立てていくものも多いです。ですから、香港での投資といえども最低投資金額は千差万別です。
投資家それぞれの運用したい資金ボリュームに合わせて、投資すべき金融商品には違いがありますので、専門家と相談しながら適切な金融商品を選ぶところから始めるのが香港での投資の基本です。
最も資金のハードルが低い香港投資とは?
数ある香港の投資のなかで最も資金のハードルが低いのは、株式と投資信託です。
株式については企業ごとの単位株の株価によりますので、投資対象とする企業によっては10万円を超えるものもありますが、優良銘柄として推薦されることが多い企業の株式であっても1万円台であることが珍しくありません。
投資信託では一括による投資か、月々の積み立てかの選択が可能な商品が多いです。こちらも月々の積み立てタイプであれば1万円台から投資をはじめることができるのが魅力です。もちろん継続して資金を入れ続ける必要がありますので、長期的な視野で投資額を決定する必要があります。
香港投資で登場する主な金融プレイヤーの一覧!
投資のための金融機能が成熟している香港では、日本では珍しいタイプの金融プレイヤーがいくつか存在しています。
香港での投資を円滑に進めるためにも、香港の金融プレイヤーの種類と、それぞれの金融プレイヤーたちが行っている業務の範囲について正確に理解するようにしてください。
銀行
HSBCに代表される香港の銀行は、資産の預け入れや定期預金などの消極的な投資に限らず、投資信託や債券を購入できる投資プラットフォームとしても機能しています。インターネットバンキングによって簡単に資金の操作ができる点では、日本の銀行と使い勝手に大差はありませんが、外貨預金として取り扱う外貨の種類の豊富なマルチカレンシー口座など香港ならではの特徴もあります。
マルチカレンシー口座とは、複数の種類の外貨を1つの口座で扱うことが可能な銀行口座のことで、HSBCの場合には米ドルや日本円を含む全12種類の通貨を預け入れることができます。
- USD アメリカドル
- JPY 日本円
- EUR ユーロ
- GBP イギリスポンド
- HKD 香港ドル
- SGD シンガポールドル
- RMB 人民元
- THB タイバーツ
- CAD カナダドル
- AUD オーストラリアドル
- NZD ニュージーランドドル
- CHF スイスフラン
HSBC香港は18歳以上であれば外国人の旅行者でも口座開設が可能ですが、以前と比べると口座を開設する難易度が上がっています。このため、HSBC香港の口座開設にあたっては、必要書類を揃え、窓口での英語でのやりとりを事前に練習するなど、十分な準備を整えてから挑む必要があります。英語に不安のある方は、サポート業者を活用するのがおすすめです。
ちなみに、世界の銀行の預かり残高のランキングでは現在、中国の銀行が上位を独占状態にあり、金融の中心が中国や香港へとシフトしていることが分かります。
銀行が破綻した場合の預金者保護のための仕組みに、ペイオフ制度があります。日本では1971年にペイオフ制度が始まり、保護の対象となる預金額が順次引き上げられ、現在では1金融機関あたり1名義で1000万円を上限として保護されます。
香港のペイオフ制度は「預金保険計画条例」に定められており、1金融機関あたり1名義で50万香港ドルを上限としています。2019年11月現在の為替レートでは、700万円弱ですので日本よりも保護の対象になる金額は少ないです。
ただし、上記の共同名義で口座を保有している場合には、2名義であるため保護の対象が100万香港ドルまで引き上げられます。一方、定期預金については5年未満のものに限られているため、5年以上の定期預金については保護の対象となりません。
なお、日本のペイオフ制度では外貨預金が保護の対象となっていません。世界の金融マネーが集まる香港では外貨預金であっても保護の対象となりますので、世界で活動する投資家を保護する制度としては香港の方が優れています。
証券会社
香港の証券会社は、株式の売買を仲介するという点では日本の証券会社と同じですが、アメリカやヨーロッパ、インド、中国、台湾、東南アジア諸国などの株式の売買が可能であるなど、香港らしく投資家に対して多くの選択肢を提供しています。ほぼ全ての証券会社がオンライントレードに対応しています。
また2013年8月には、日本のオンライン証券会社として有名なマネックスグループが参画したことで話題の日系のNWB(Nippon Wealth Limited)が設立され、日本語環境による投資提案などを行っています。NWBは新生銀行が中心となっており、日本政策銀行とあすかアセットマネジメントのJVであるマーキュリアインベストメントからも出資を受けています。
金融プロバイダー
香港の投資では頻繁に登場する金融プロバイダーは、投資信託や保険などの金融商品を設計して運用する金融スペシャリストです。ただし、金融プロバイダーは自ら金融商品を販売する窓口を持っていないため、一般投資家はIFAを通じて金融プロバイダーが運用する商品に対して投資を行うことになります。
独立系金融アドバイザー(IFA)
金融プロバイダーが設計して運用する金融商品の販売窓口となっているIFAは、香港投資のためのガイド役のような存在です。ただし、金融プロバイダーの販売代理店のような存在ではなく、それぞれの金融商品が投資家にとってメリットがあるものであるかを厳しく精査しており、質の悪い金融商品に投資家を近づけない門番のような役割も担っています。
IFAについては、次の項目でさらに詳しく解説します。
香港投資のワンストップサービス、独立系金融アドバイザー(IFA)とは?
香港の投資をはじめる方にとって心強い存在となるのが、独立系金融アドバイザー(IFA)の存在です。IFAとは「Independent Financial Adviser」の略称で、日本の「投資顧問会社」に近い存在である香港投資のプロフェッショナル会社です。
もちろん、さまざまな金融商品を販売している個別の金融機関や運用会社を訪問して契約することも可能ですが、IFAを活用することで香港投資のワンストップサービスを受けられ、最適な運用方法の提案だけではなく、実際の運用そのものを任せることができます。
販売委託会社とIFAの違いとは?
投資や金融の世界にはさまざまなプレイヤーが存在しており、IFAと似たような営業形態の業種として販売委託会社があります。販売委託会社とは、その名の示す通り、金融機関や運用会社から販売を委託された投資商品を、顧客に対して販売することを事業としています。
一方、IFAも独自の金融商品を運用しているのではなく、顧客に対して金融機関や運用会社が扱う投資商品を販売することが主な事業となります。ただし、販売委託会社が商品の販売手数料で収入を得ているのに対して、IFAは顧客の資産の運用実績によって収入が発生する仕組みとなっており、顧客側の立場に立った運用を行う点が大きく違います。
IFAが持っている国家資格とは?
日本では投資顧問会社の定義が曖昧で、会計士やファイナンシャルプランナー、宅地建物取引主任者などの資格を持った人々が代表となり、投資家に対して資産運用の提案を行っています。また、銀行や農協などのスタッフが投資のアドバイスを行うこともあります。
香港でIFAの看板を掲げて営業を行うには、保険に関する専門会社が所属する2つの協会や、証券や先物を扱う事業者が所属する委員会のうちのいずれかに登録されている必要があります。これらの資格を持たずにIFAのような投資アドバイス事業を行うことは、最長7年の禁固刑あるいは最高500万香港ドルの処罰の対象となります。
香港保険顧問協会(CIB)
CIB(Confederation of Insurance Brokers)は、投資商品として保険を取り扱うIFA事業者が登録する協会です。単なる同業種の集まりではなく、一定の条件を満たした事業者のみが登録を許される認定機関としての機能を持っています。
CIB登録ライセンスの取得には、資本金や専門性などが厳しく審査されるため、投資家が投資アドバイスを受けるIFAを選ぶ際にはライセンスの取得の有無が重要な判断材料となります。
香港保険業協会(PIBA)
PIBA(Professional Insurance Brokers Association)は、CIBと同じく保険を取り扱う事業者が登録する協会ですが、CIBと比較すると登録の難易度が低いため、登録しているIFAの数が多いことが特徴です。
PIBA登録のIFAであることが即座に質の悪いサービスを提供しているとは言えませんが、SFCライセンスを保有していないPIBAのみ登録のIFAに対しては少し警戒する必要があります。
香港証券先物委員会(SFC)
香港発の金融恐慌(ブラックマンデー)を受けて1989に設立された証券と先物に関する投資のプロフェショナル企業のみが登録を認められる組織です。正式名称は「Securities and Futures Commission」で、頭文字をとってSFCと呼ばれます。
SFCが提供するライセンスは1から10のタイプに分類されています。
- タイプ1 証券にかかわる取引の許可
- タイプ2 先物にかかわる取引の許可
- タイプ3 外国為替証拠金取引に関わる取引の許可
- タイプ4 証券にかかわるアドバイス業務の許可
- タイプ5 先物にかかわるアドバイス業務の許可
- タイプ6 法人財務にかかわるアドバイス業務の許可
- タイプ7 自動売買サービスの提供の許可
- タイプ8 株担保融資の提供の許可
- タイプ9 アセットマネジメント(資産管理)業務の許可
- タイプ10 投資商品の格付け業務の許可
これらのSFCライセンスは会社ごとに1つずつではなく、1社が複数のライセンスを取得することが可能です。ただし、各タイプごとに資本金や専門性などの審査基準が設けられており取得は容易ではありません。
投資信託にかかるアドバイスや運用委託をSFCに依頼する場合には、タイプ1、タイプ4、タイプ9を取得しているかどうかを確認してください。
IFAの運用実績を知る方法とは?
香港での投資に関する全てを任せることになるIFAですから、最も気になるのは過去の運用実績です。しかし、多くのIFAでは運用実績を一般公開していないため、個別に問い合わせを行う必要があります。
特にリーマンショックの発生した2008年以前の運用実績については公開されていることが極めて珍しいため、金融有事の際の対応力について公開情報だけでは判断することが難しいです。事前にある程度の数までIFAを限定し、個別に問い合わせることで情報を得ることが重要になります。
信頼できるIFAに出会う方法とは?
保険に関する2つの協会やSFCでライセンスを取得しているIFAの総数は200社以上にものぼります。日本の証券会社の数が260前後で推移していることと比較すると、香港の投資環境の充実ぶりが感じられます。
IFAはそれぞれに得意分野があり、扱う顧客層も細分化されているため、200社以上のなかから日本の個人投資家に最適な事業者を見つけることは大変な作業になります。
IFAに直接問い合わせる
香港のIFAの多くはウェブサイトを開設していますので、メールや電話で問い合わせを行うことが可能です。
ただし、IFAは世界の投資家たちを顧客対象としていますので、基本的な問い合わせは英語であることに加え、香港の投資に関する基礎的な知識を十分に持っていることを前提とした回答しか返ってきませんので、はじめて香港で投資をされる方には直接の問い合わせはハードルが高いです。
紹介によってIFAと出会う
香港は欧米の文化を多分に含んだ商習慣であるため、紹介によってコンタクトした顧客を重んじる傾向にあります。また、紹介によってIFAと出会うことにはいくつかのメリットがあります。
すでに香港投資を行っている投資家や専門家を通じてIFAの紹介を受けることによって、香港オフィスへの訪問の日時を設定することが容易になるだけでなく、日本国内でIFAと接触することも可能になります。IFAによっては日本国内で契約を済ませることができるケースもあります。
ただし、あまり香港の投資に詳しくない投資家や紹介者を経由することで、不本意な契約をしてしまうケースや、実績に乏しいIFAを紹介させるケースも多いですので注意が必要です。香港投資に精通した専門家に問い合わせを行うことをおすすめします。
香港での投資の最初から最後までの全ステップとは?
いざ香港で投資を始めるにあたっては、どのような手続きやステップが必要なのでしょうか。
ここからは具体的に香港で投資をするために必要なこと、また投資で儲けた収益を日本に戻す方法など、香港投資をゼロから始めるための全ステップをわかりやすく解説します。
せっかく香港で投資をしたものの思っていたことと違ったという失敗をしないためにも、日本国内投資とは異なるポイントをしっかりチェックしてください。
日本から香港へ投資資金を移転させる方法とは?
香港で投資を始めるためには、日本にある日本円の資産を、香港の金融機関へと移転させなければなりません。
日本から香港への投資資金の移転方法は、香港で利用する金融機関によって違いがありますので、銀行および証券会社とFIAを活用する場合の2つに分けて、わかりやすく解説します。
香港の銀行・証券会社へ投資資金を預け入れる場合
HSBCなどの香港の銀行や証券会社を通じて投資を行う場合には、まず初めに口座を開設することが必要です。
最初に香港での投資をはじめるにあたっては、現金をハンドキャリーで持参します。ただし、ここで注意しなければならないのが現金の持ち出しと持ち込みに関する申告義務です。日本からの持ち出しは100万円以上、香港への持ち込みは12万香港ドル以上で、それぞれの申告義務が発生します。
マネーロンダリング対策には各国政府が力を入れていますので、申告せずに多額の現金を持ち運びすることがないように注意してください。
なお、香港に銀行口座を開設後は、自分名義の日本と香港の銀行口座間での国際送金も選択肢のひとつとなりますので、必ずハンドキャリーをしなければならないのは初回のみです。
香港への投資目的に限らず、100万円を超える現金、有価証券(株式、債券)などを持ち出す場合には、出国手続きを行う空港の税関に備え付けられている「支払手段等の携帯輸出・輸入申告書」に記入してください。
記入内容は氏名や住所、持ち出す金額など10項目以下の簡単なものです。普段の海外旅行よりも少しだけ時間に余裕を持って空港に向かえば、特に問題はありません。
IFAに対して投資資金を預け入れる場合
IFAを通じて香港で投資を行う場合には、日本国内でIFAとの契約を済ませたうえで、投資資金をIFAの口座へと送金することになります。IFAによる資産運用では、一括で投資資金を入れるのではなく月々の積み立て投資を行う方がメリットがあります。
クレジットカードで投資資金を預け入れる
毎月の積み立てを日本のクレジットカード払いとすることによって、日本から香港へとスムーズに資金を移動させることが可能になります。
クレジットカードに限定することで投資対象が少なくなってしまったり、カード利用限度額の制約を受けたりするデメリットがありますが、手軽に投資を開始するにはクレジットカード払いが有効な選択肢のひとつです。
ただし、クレジットカードでの投資と言えども、金融商品の申し込みのためには必ず一度は香港へと足を運ぶ必要があります。
銀行(HSBCなど)の口座から自動引き落とし
IFAへの月々の積み立てを銀行からの自動引き落としとすることも可能です。
香港の銀行口座にまとまった資金を入れておくことで、有利な為替レートのタイミングで米ドルへの両替ができる点が大きなメリットです。
月々の引き落としには十分すぎる資金がある場合には、投資口座を通じて独自の運用を行ったり、マルチカレンシー口座の利点を活かして為替による差益を得る運用を行うこともできます。
香港から日本へ投資利益を移転させる方法とは?
せっかく香港の投資で収益を上げることができても、日本へと利益を移転させることができなければ”絵に描いたモチ”になってしまいます。
しかし、既に日本と香港に銀行口座がある状態ですから、香港への投資資金を移転させることと比べるとさほど難しい問題はありません。
現金のハンドキャリーについては、日本では持ち出し時と同じく100万円を超えた場合には申告が必要になりますが、その他の代替手段が数多く考えられます。
国際間送金で利益を受け取る
香港で運用していた多額の投資資金をまとめて日本へと送金したい場合には、国際間送金を利用します。HSBC香港から日本の銀行口座へと直接、国際間の銀行送金を行うことが可能です。インターネットバンキングで手続きが完結しますので、わざわざ香港の窓口へと出向く必要はありません。
なお、一度に1万香港ドル以上を送金するためには送金限度額の上限引き上げの手続きが必要になり、40万香港ドル以上の場合には事前に銀行口座の登録申請を済ませておく必要があります。
HSBC香港から日本を含む国外への送金手数料は1回あたり115香港ドルで、送金手数料や為替レートが気になる方はトランスファーワイズなどの送金サービスを利用することも検討してください。
日本全国のATMから引き出す
HSBC香港のキャッシュカードは、6大国際ブランドのひとつである中国銀聯(UnionPay)と提携していますので、日本を含む世界170か国以上のATMで現金の引き出しが可能です。日本では三菱UFJ銀行、三井住友銀行のATMが引き出しに対応しています。
国際ブランドとは、世界での決済ネットワークを保有しているクレジットカードのことで、VISA、マスターカード、JCB、アメリカンエキスプレス、ダイナース、中国銀聯(UnionPay)が6大国際ブランドです。
香港の外のATMでの引き出しには1回あたり20香港ドルの手数料が発生し、また日本などの現地銀行でのATM利用料が請求されます。このため、ATMで引き出す場合には細かな金額を繰り返し引き出すのではなく、ある程度のまとまった金額を引き出すように心掛けてください。
クレジットカードで使う
HSBC香港では、口座の種別に応じてVISAやマスターカードがついたクレジットカードを発行することが可能です。UnionPayと比較しても加盟店が圧倒的に多い国際ブランドですので、日本でも海外でもクレジットカード決済ができる機会が増えます。
渡航不要で香港の投資を始めることは可能?
香港での投資について資金的な問題ではなく、時間的な問題によってスタートをためらっている投資家の方もいます。日本国内でのビジネスやご家族の事情によって、香港へと足を運ぶための時間が確保できないという方々です。
現実的には香港の一部の銀行では、海外からの書類送付だけで口座開設を受け付けています。ですから渡航不要で香港投資が可能であるかどうかという疑問に対しては「可能である」との回答にはなるのですが、これはあまりに不親切な回答です。
なぜなら、海外から書類だけで口座を開設することが可能な香港の銀行が、必ずしも投資家にとってベストな環境を整えているわけではないからです。
最初の1回の香港への渡航については必ず行かなければならないという前提で、香港での投資を検討されることをおすすめします。
香港駐在員たちは本帰国前に投資を始める
金融と貿易の都市である香港には、日本の大手商社や金融機関の駐在員たちが数多く生活しています。駐在員の多くは3年から5年で任期を終了して日本へと本帰国することになりますが、任期中あるいは本帰国直前までには必ず香港での投資を始めます。
香港で生活をしていると勤務先の業種を問わず金融や投資に関する知識が増えますので、任期中に貯めた資金を持ち帰ることなく香港での投資に充てるのです。
駐在員が香港滞在中に投資を始めるのは、やはり香港での投資は現地で手続きを行うことがベストであるとの共通認識があるためです。彼ら(彼女ら)には香港で手助けしてくれる友人や知人がいますが、それでも日本から遠隔で手続きを行うのではなく、香港で投資をスタートさせるのです。
香港での投資効率を最大化する再投資の方法
香港での投資で得られた収益は、差し迫った資金の使い道が無い場合には再投資を続けることが好ましいです。なぜなら香港で販売されている金融商品の大半は、再投資による複利効果を狙った設計になっているため、収入が発生するごとに引き出す必要がないからです。
不動産などの実物資産と比較した場合、投資信託などの金融商品は再投資がしやすく、資産効率を最大化させることができるのがメリットのひとつですので、香港の投資環境を上手く活用するためにも長期的な計画に基づいて投資を行ってください。
再投資を上手く行うには銀行や証券会社だけでなく、独立系金融アドバイザー(IFA)を活用することが好ましいです。両者の違いについて確認しましょう。
香港の銀行・証券会社に口座を開設して商品を買う方法
香港の銀行・証券会社(HSBCなど)に口座を開設することによって、株式や投資信託などの金融商品を購入して、すぐに投資をはじめることができます。投資商品のラインナップの豊富さを実感する一方では、あまりの多さにどれに投資すれば分からないと困惑してしまいます。
投資で得られた収益を再投資する場合にも、やはり豊富な投資商品の中から最適な投資先を選択し、自由に購入することができます。自ら選んだ株式の価格が上昇したり、投資信託が十分な結果を出しているときには、大きな満足感が得られます。
HSBCなどの銀行の投資口座を活用することによって投資信託の購入を行うことが、もっともシンプルな香港での投資スタイルです。インターネットバンキングと同じ操作で、世界の投資商品にアクセスすることができます。
香港のIFAを通じて再投資を行う方法
先ほど紹介したIFAとの契約を行うことによって、金融のプロが選択した投資先へと効率的に投資を行うことができます。常に変化を続けるマーケットの最新情報を追いかけ、最適な投資を行ってくれるので、やはり香港での投資の醍醐味はIFAの活用です。
全ての投資資金を一気に引き上げることには制約が設けられることがIFAを通じて投資を行うデメリットとなりますが、長期投資を前提に再投資を繰り返す運用を行う場合には、IFAに投資を一任する方が好ましい投資成果が得られる場合が多いです。
IFAとの契約後は、個別の株式や投資信託について精査する必要もなく、毎月の積み立てを行うことによって資産が運用されますので、安心感があります。ただし、IFA選びを間違わないことが大前提ですので、この点には十分に注意してください。
損しないために知っておきたい手数料の基礎知識とは?
香港の投資では、右も左も分からない海外での投資ということもあり、不要な手数料を支払ってしまう詐欺に相当するような被害がたびたび発生しています。日本では当然と思われるような手数料であっても、香港では発生しないケースが多いですので基礎知識として確認しておきましょう。
香港の金融商品の販売手数料とは?
日本では通常、金融商品の販売では手数料の支払いが必要になります。金融商品について分かりやすく解説を受け、諸手続きのアドバイスをしてもらった代価として販売手数料を支払うことが当然のように感じますが、香港ではノーロードと呼ばれる手数料が無料となっている販売形態が多いです。
投資信託で発生する信託報酬とは?
信託報酬とは、投資信託の販売、運用、管理にかかる全ての業務に対する手数料の総称です。さきほど販売手数料がかからないと説明しましたが、正確には販売手数料も信託報酬に合算されているので、投資家が負担することになります。
投資家から手数料を取らないIFAの収益モデル
販売手数料がないノーロードの商品を販売してもIFAが儲かるビジネスモデルとは、信託報酬から利益が得られることを意味しています。信託報酬は、販売価格に上乗せされたり、販売価格の一部から支払われるのではなく、あくまで投資運用益から差し引かれるものです。
このため、IFAでは顧客を儲けさせることを大前提として、顧客の儲けの一部を報酬として受け取る仕組みになっています。顧客とIFAのどちらもが投資によって利益を上げるという同じ方向を向いていますから、利益の相反が起こらず、運命共同体としてお互いのパートナーシップを組むことができます。
現実の利益はどれくらい?香港の長期投資シミュレーション
ここまでに解説した内容を総動員して、香港で投資を行った場合の利益がどれくらいになるのかについて長期投資シミュレーションを行ってみましょう。日本人が投資をしやすい投資対象として投資信託を想定して利益を算出します。
長期投資で生まれる複利の効果
日本の投資信託は毎月配当や毎年配当が基本であるため、毎年の分配金に対して所得税等の20%が引かれ、再投資には販売手数料1%以上がかかります。例えば年間に5万円の分配金があったとしても、再投資できる金額は3万9000円程度になります。
しかし、香港の場合には毎年の利益は分配されずに再投資されるため、年ごとの所得税や販売手数料は発生しません。このため、5万円の収益があった場合には、5万円がそのまま再投資されます。
香港の場合でも最終的には投資収益の総額に対して約20%の所得税がかかりますが、運用期間中は利益を全て再投資して、複利効果を最大限に活かすことができます。
長期投資で活かせるドルコスト平均法
香港を含む海外での運用でのデメリットのひとつは、為替リスクがあるということです。この為替リスクを最小限に抑える方法として有効なのが、ドルコスト平均法の活用です。毎月の積み立てによってドルコスト平均法が機能して、為替リスクが飛躍的に軽減されます。
ただし、日本国内で円建ての投資を行っている限りにおいては為替リスクは発生しませんので、ドルコスト平均法については海外投資のデメリットを補っているに過ぎません。
過去10年間のドル円相場を見ると、一時的には1ドル80円を下回っていたこともあり10年の平均が1ドル100円ちょうど台となっており、現在の1ドル109円近辺の相場と比べると結果的には為替変動のメリットを享受する形となりました。
もしも10年前に香港で投資を始めていた場合の収益とは?
では、2010年1月から毎月2万円を香港の投資信託に投資し続けた場合の収益を算出します。あまりに利益率が高すぎる投資信託で計算しても意味がありませんので、毎年10%の収益をあげた香港の標準的な投資信託の数字を用いてシミュレーションを行います。
月々の2万円は各年の平均為替レートで米ドルに換金して運用することとします。また利益については、やや正確さを欠きますが各年の運用総額に対して年利率をかけて算出しています。
| 運用額(米ドル) | 利益(米ドル) | |
|---|---|---|
| 2010年 | 2,736 | 273 |
| 2011年 | 6,007 | 600 |
| 2012年 | 9,587 | 958 |
| 2013年 | 12,957 | 1,295 |
| 2014年 | 16,521 | 1,652 |
| 2015年 | 20,157 | 2,015 |
| 2016年 | 24,382 | 2,438 |
| 2017年 | 28,960 | 2,896 |
| 2018年 | 34,028 | 3,402 |
| 2019年 | 39,632 | 3,963 |
10年の運用の結果、4万3596ドル(運用総額3万9632ドル+最終年の利益3963ドル)が手元に残りました。2019年11月現在の為替レート(1ドル109円)で日本円に戻すと、475万1992円です。総投資額は240万円ですので、投資信託の利益235万1992円から所得税20%を差し引いた税引き後の資産は428万1594円となります。
総投資額:240万円
総資産額:428万1594円
総利益額:188万1594円
この利益と同じ金額を日本の投資信託で得るためには、複利効果が働きにくいことから、日本では年利率16.7%の投資信託での運用が必要になります。高い利回りの商品には高いリスクが伴いますので、香港での運用の方が圧倒的に優れていることが分かります。
香港の投資まとめ
アジアを代表する金融センターである香港では、世界水準の投資を実現することができます。渡航が必要であることや為替リスクが発生することを考慮しても、やはり香港を活用することは日本の個人投資家にとって有効です。
海外での資産運用というと大富豪が行うものというイメージがありますが、個人投資家であっても十分に投資が可能な金額からさまざまな投資商品が香港にはあります。
近年では日系の金融機関が香港法人を設立するなど、香港での資産運用を行う日本人が増加する傾向にあります。
香港での投資では、IFAという独立系の投資顧問会社を活用することがスタンダードで、日本国内で事前に紹介を受け、書類の準備の段階からアドバイスをもらうことが香港投資をスムーズに始める秘訣です。
香港の投資をできるだけ早く始めるべき理由とは?
投資の世界では、お金と時間をかけるほど利益は大きなものになります。このため、投資では早く始めることにはメリットしかありません。
また、香港に関しては現在、マネーロンダリング対策によって新規顧客の受け入れが徐々に厳しさを増しています。このため、投資のスタートが遅くなるごとに必要書類が増えたり、面談等のステップが増え、投資のハードルが上がってしまいます。
これまでにも香港の規制は徐々に高まってきましたが、既存の顧客に対して新たな規制が適用されたり、不利なルールが追加されたことは一度もありません。
香港投資に興味が沸いた方は是非、次のステップへと第一歩を踏み出してください。