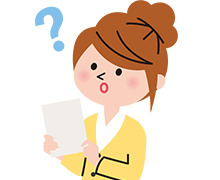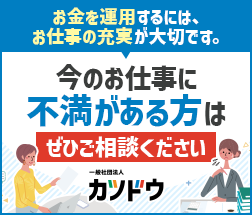ブラジルファンド、アジアファンド、エネルギーファンド、AIファンド、ロボット・テクノロジーファンド……こうした名称の商品はたいていテーマファンドと呼ばれる投資信託で、証券会社などの人気ランキングでもたびたび上位に食い込んでいます。
しかし資産運用の観点から見ると、テーマファンドは非常に問題の多い商品であることがわかります。
実際、ネットや書籍、雑誌などでもファイナンシャルプランナーがテーマファンドへの警鐘を再三にわたって鳴らしています。
にもかかわらず、テーマファンドは売れ続けています。なぜならそれは、金融機関にとってこれほどおいしい商品はないからです。
ここでは金融機関から見たテーマファンドのうまみを明らかにするとともに、テーマファンドが投資家の資産運用に向いていない理由も解説していきます。
金融機関目線で考える「テーマファンド」のメリット
売りやすい
冒頭で挙げた例のように、テーマファンドは名前の通り何かしらのテーマに沿って作られている商品です。
「エネルギーファンド」なら石油のようなエネルギー資源の価格が上昇しているときに作られますし、AIやロボット・テクノロジーも関連企業の株価が上昇しているときに作られます。
テレビや雑誌、ネットなどでも話題になっているテーマを選ぶので、窓口の担当者が投資家に対して営業トークを展開する際も、「今、AIが話題になっておりまして……」などと切り出せば「ああ、確かによく聞くよね」とスムーズに話が進みます。
また、テーマファンドを作ると金融機関は「今期はこのテーマファンドを○○○○億円売りましょう」という形で全社を挙げて販売しようとします。
すると資金調達がものすごい勢いで進むため、投資家を勧誘する際も「今このファンドは非常に人気なんです」という形で購買意欲を刺激することができるわけです。
話題性と人気が集中すれば、自然と基準価額も上昇していきます。
そうなれば「これからもっと上がるかも」「それなら今のうちに買っておいた方が利益が出るかも」という投資家の期待感をくすぐるのは簡単です。
儲けやすい
テーマファンドには売りやすいということに加えて、儲けやすいというメリットもあります。
というのもテーマファンドのように資金調達額にしろ、基準価額にしろ、勢いのある商品には漠然とした「今後も上がり続けるだろう」という期待を持たせる力があります。
そのためこの投資信託は、他の商品に比べて割高の手数料を設定していても売れていくのです。
また投資信託を売却したり、購入したりするためには解約手数料(*)や販売手数料がかかる場合がありますが、テーマファンドはこうした手数料が入りやすいという性質もあります。
というのもこの投資信託は一過性のブームに当て込んで作っている商品なので、近い将来にブームが過ぎ去ると「もうこの商品は旬じゃない」と考えて売りに出す人が増えるのです。
結果金融機関の手元には売却時の解約手数料と、買い替え時の販売手数料が入るというわけです。
*解約時に必要な手数料としては解約手数料以外に、「信託財産留保額」というものがあります。
これは解約時に証券売買などでかかるコストを徴収する目的で設定されています。
だからいつでもランキング上位
売りやすく、儲けやすいので、金融機関は積極的に営業をします。
金融機関の窓口で投資をしようという一般的な投資家にとって担当者は専門家ですから、その専門家が言うことは正しく聞こえてくるものです。
担当者が「このアジアファンドが今人気でして」「AIはこれから必ず伸びるので、このファンドがおすすめです」などと言えば「そんなものなのかな」と感じて購入してしまいます。
だからテーマファンドはいつでもランキングの上位に食い込むのです。
テーマファンドが資産運用に向いていない理由
これだけ売り手にとって理想的な商品だということは、買い手である投資家にとって何かしらの問題があるということは容易に想像がつきます。
ではどういう点において、テーマファンドには問題があるのでしょうか。
一過性のブームをもとに作られているから
テーマファンドが抱えている買い手にとっての最大の問題は、この投資信託が一過性のブームをもとに作られている点にあります。
- アジア株がこれから伸びる。
- ロボット・テクノロジー株がこれから伸びる。
そういった情報をいち早く手に入れるのは、金融機関に務めるプロの投資家や、金融機関の上客になっている一部の富裕層です。
彼らはまだ価格の安い「これから伸びる分野」に潤沢な資金を大量に注ぎ込んでいきます。
資金が調達できてその分野がさらに伸びていくと、テレビやネットでも少しずつ話題になります。
するとそのタイミングで、金融機関が「この分野のテーマファンドを作ったら、きっと売りやすいし、儲けやすいぞ」と考えて、企画を立て、全社一斉にプロモーションをスタートさせます。
「このファンド、ものすごい勢いで伸びておりまして、みなさん慌てて買い替えておられますよ」
「でもそんなに勢いよく伸びているなら、どこかで失速して下落するでしょう?」
「たしかにそうですが、そのタイミングで売りに出せば利益が残ります。その利益で他の商品を買っていただければ、十分資産運用になりますよ」
「(なるほど……そうだな。あまり欲を出さずに早めに売れば大丈夫か。)わかりました。話を進めてください」
ある窓口ではこんなやりとりが展開されているかもしれません。
しかし最初に資金を注ぎ込んだプロの投資家や一部の富裕層は、その頃すでに「この分野のブームは近いうちに落ち着くだろう。そろそろ潮時だな」と考え始めています。
そして最初に比べて圧倒的に割高になったテーマファンドが一般の投資家たちに行き渡った頃、プロの投資家や一部の富裕層が「この分野はもう伸びきった」と判断して関連企業の株を売りさばきます。
彼らの資金力は一般投資家の比ではありませんから、市場の価値は一気に下落します。
当然テーマファンドの基準価額も大きく下がります。
結果、一部の人間は大きな利益を出す一方で、一般投資家の大半は損失を出すことになるのです。
「老後のための生活資金を、現役時代のうちからコツコツ作っていこう」という大半の投資家にとって、資産運用は基本的に長期スパンで考えるべきものです。
にもかかわらず、テーマファンドは最初から一過性のブームに合わせる形で作られる商品です。
しかもこの投資信託が売りに出されたときにはすでにブームは終わりはじめているので、よほど早いタイミングで売りに出さなければ損失を出してしまいます。
だからテーマファンドは資産運用に向いていないのです。
手数料がかさみやすいから
今「よほど早いタイミングで売りに出さなければ」と書きました。
しかし当然ながら、早いタイミングで売りに出すと、損失を回避できるぶん、利益を得られることもありません。
ところが損失が出ていようが、利益が出ていまいが、契約時に設定された解約手数料はかかりますし、買い替えをするには手数料がかかります。
仮に販売手数料が2%、信託報酬(ファンドの管理コスト)が1.5%だったとすると、1,000万円をテーマファンドに投資した半年後には、27万5,000円を金融機関に支払っていることになります。
ここに解約手数料や信託財産留保額などが加わり、かつ買い替えをする場合はその商品の販売手数料も必要になるわけですから、資産はさらに目減りします。
こんなことを繰り返していれば、「老後の生活資金をコツコツ作る」どころか、資産が減っていく一方です。
そもそも「分散投資」になっていないから
またテーマファンドは、投資信託の本来の役割から考えてみても、資産運用に向いていないことがわかります。
投資信託の最大のメリットは、少額からでも世界中の様々な株式や債券に分散投資ができるという点にあります。
これにより、たとえばアメリカ経済が多少落ち込んでも、他の地域の経済が盛り返すことで結果的に損失を回避できるのです。
しかしテーマファンドは、テーマを設定することで分野や銘柄を絞り込んでしまっているため、前提からして分散投資にはなっていません。
そのためアジアの株が下落したり、AIブームが過ぎたりすれば、その影響をダイレクトに受けます。
こうした視点から考えても、テーマファンドは資産運用に不向きなのです。
まとめ
テーマファンドは金融機関にとって、売りやすく、かつ儲けやすいという理想的な商品だと言えます。
だからこそ金融機関は優先的にテーマファンドの勧誘を行うわけです。
その一方で、この投資信託は投資家にとっては百害あって一利なしの商品です。
一過性のブームに乗じて作られているために長期運用には向いておらず、値崩れもしやすいうえ、手数料もかさみやすいというデメリットがあります。
加えてそもそも分散投資にもなっていないため、投資信託の本来の役割であるリスクヘッジの効果もほとんどありません。
したがって、たとえどんなに人気の商品であっても、テーマファンドには手を出さないのが賢明だと言えるのです。