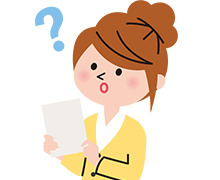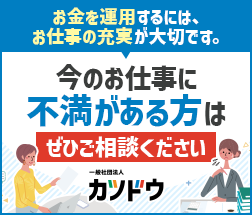「法人化は節税になる」と聞いたことはないでしょうか?
実業家はもちろん、テレビに出る芸能人も法人化していたりしますが、法人化がなぜ節税につながるのか実はよくわからないという方は多いと思います。
法人化で節税できるポイントは大きく3つあります。
なぜ実業家や芸能人が法人化するのか、その仕組みを確認しておきましょう。
法人化で節税できる3つのポイント
税率が違う
個人の所得税は「累進課税」といい、所得が上がるほど税率が高くなっていきます。
例えば年間の所得が200万円なら所得税は約19万円で税率は約9.5%ですが、所得が1,000万円だと約279万円で税率は約28%にもなってしまいます。
一方、法人税は固定の税率で、2019年4月以降では23.2%です。
法人の区分や資本金により税率が多少変わりますが、基本的に固定の税率で計算されます。
所得が一定を超えると、個人の所得税より法人税の方が税負担が軽くなるのです。
経費と各種控除の二重利用
法人を設立した人(いわゆる社長や役員)は、法人から給与などの名目で資金を引き出します。
引き出した資金は社長個人の所得税の対象となりますが、あくまで給与ですから各種の控除が利用可能です。
給与なら自動的に税金を安くしてくれる「給与所得控除」が利用でき、退職金なら「退職所得控除」が利用できます。
法人にとって給与は経費なので、法人税の減額にもつながるのです。
法人税は「必要経費(損金)」で減らせ、社長個人の所得税は各種の控除で減らせます。
節税を二重で考えるため、法人化は節税につながるのです。
貯蓄性の高い経費
法人で計上できる経費のうち、貯蓄性の高いものがあります。
例えば100万円支出し、100万円返ってくるというようなもので、実質的に費用の掛からないものです。
費用0で税金だけ安くなる、非常に有効な手段だといえるでしょう。
公的なものでは「セーフティ共済」 や「企業型確定拠出年金 」などがあります。
法人がこれらから資金を受け取ると益金として所得に計上され、社長や役員への退職報酬などで相殺する手段が取れるのです。
返戻率の高い民間の保険も利用できます。
ただし、民間の保険については経費計上のルールが厳しくなり、節税の効果が薄れてしまいました。
詳しくは後述します。
その他の法人化のメリット
家族を役員にすることで控除を複数適用できる
上述した給与所得控除は、給与を受け取る方にそれぞれ適用されます。
これを利用するとさらに節税が可能です。
例えば家族を法人の役員にし、法人から給与として資金を払い出します。
給与所得控除は最高で1人195万円までしか適用されませんが 、複数で受け取れば世帯で考えた時の税負担を減らせます。
損失を繰り越しできる期間が長い
事業を行っていると赤字になってしまう年があるでしょう。
この赤字を翌年以降の黒字と相殺させることを「損失の繰り越し(欠損金の繰り越し)」といいます。
例えば前年に100万円の赤字で、本年100万円の黒字が出るとします。
2年で考えると損益は0のはずですが、今年の黒字に対して税金が発生してしまいます。
前年分の損失を繰り越し、本年分の黒字と相殺させれば税金は発生しません。
個人のまま事業所得や不動産所得を得ていても、「青色申告」を利用すれば3年間は損失の繰り越しができます。
法人なら9年間繰り越せます。
不動産の相続税を少なくする可能性
不動産を個人のまま所有しておくと、相続発生時は時価評価となります。
土地は路線価などで、家屋は固定資産税評価額で相続税が計算されます。
不動産を法人所有とすると相続税の評価はその法人の価値で計算されるため、法人の株式を遺族が相続するという形式です。
未上場の株式を相続したときの評価は、一般に「純資産価額方式」で評価されます。
法人が持つ総資産から負債などを引いた金額により評価する方法で、計算方法の違いが相続税の違いにつながるのです。
しかし、個人の場合でも「小規模宅地等の特例」などを利用すると相続税が有利になる場合があります。
個人の方が有利になる不動産の場合、個人所有としておいた方がよいでしょう。
主な法人化の注意点
法人事業税など、法人税以外の税金に注意
法人が支払う税金は法人税だけではないという点に注意しましょう。
個人でも国税である所得税のほか、住民税などの税金が掛かりますよね。
法人も法人税以外に「法人事業税」や「法人都民税(県民税)」などを納める必要があります。
また「消費税」も納付する義務があります。
法人税だけでなく、すべての税負担を考え法人化を検討しましょう。
社会保険料の負担
法人化させると、その従業員は原則「厚生年金」と「健康保険」の加入対象者になります。
合わせて「社会保険」といいますが、社長や役員も加入対象者です。
社会保険の保険料は「労使折半」といい、法人と法人の従業員が同じ額を支払う必要があります。
一定以下の従業員は社会保険に加入させる必要はありませんでしたが、近年その基準が変更され、多くの従業員が加入対象者となりました。
法人の社会保険の負担は小さくありません。節税だけでなく、社会保険の負担も考えて法人化を判断しましょう。
法人保険の取り扱いが変更に
貯蓄性の高い経費として、これまで返戻率の高い民間の保険が活用されてきました。
保険料を経費として計上し、必要なときに解約し資金を得るという方法ですね。
預貯金に近い使い方ができ、かつ節税できる方法で人気がありました。
しかし、貯蓄性の高い保険の保険料を法人の経費として計上するルールの変更が行われました。
返戻率の高い保険の保険料は、その全額を経費として計上できなくなってしまったのです。
法人保険の改悪
2019年7月以降は法人保険の取り扱いが規制された
法人が節税を目的に返戻率の高い保険を契約する行動を問題視した国税庁は、ルール改正の通達を出しました。
それまで各保険の種類ごとに定めていた経費計上のルールを破棄し、経費計上できる金額は返戻率を基準に判断するようになったのです。
これまでは死亡保障の定期保険であれば、返戻率がいかに高くても保険料の全額を損金として経費に計上できていました。
経費計上できる額を返戻率に基づき判断することによって、この手法が大きく制限されてしまいました。
2019年6月以前に契約した保険は従来通りですが、2019年7月以降の契約は新ルールが適用されます。
解約返戻率が高いものは全額の経費計上が禁止に
| 最高解約返戻率 | 経費計上が制限される期間 | 計上できる経費の割合 |
| 50%以下 | なし | 保険料の全額 |
| 50%超、70%以下 | 保険期間の当初4割 | 保険料の6割 |
| 70%超、85%以下 | 保険期間の当初4割 | 保険料の4割 |
| 85%超 | 保険期間の当初から、最高解約返戻率に到達するまでの期間 | ①当初10年は最高解約返戻率の1割 ②11年目以降は最高解約返戻率の3割 |
法人が契約する保険の保険料をどれくらい経費に計上できるかは、保険期間で最も高くなるときの解約返戻率で判断されます。
返戻率が最高でも50%までにしかならない保険は、従来通り保険料の全額を経費に計上可能です。
最高解約返戻率が50%を超えると計上できる経費が制限されます。保険料のうち、経費に計上できない部分は「資産」として計上されることになります。
資産に計上されると経費扱いされず、節税効果はありません。
経費計上が制限される期間が終わると、保険料の全額+計上してきた資産の一部が経費として計上されますが、解約返戻率も減少していきますので保険の貯蓄性が薄れていきます。
いわゆる「掛け捨て」の状態に近づいていくんですね。
掛け捨ての保険ならまさに費用ですから経費計上できて当然です。
新しいルールの制定で、民間の保険ができる節税策はかなり制限されてしまったと言わざるを得ないでしょう。
一定以上の高所得者は法人化で節税できる
個人のままだと累進課税により、所得が上がるほど課税税率が上がってしまいます。
法人税の税率は約23%でしたが、個人の所得税だと所得が900万円以下までは23%以下となり、900万円超だと法人の税率を超えます。
900万円の所得が法人化を検討する1つの目安といえるでしょう。
法人化には他にもメリットがあり、またデメリットもありました。法人化をする場合はよく検討し慎重に判断しましょう。