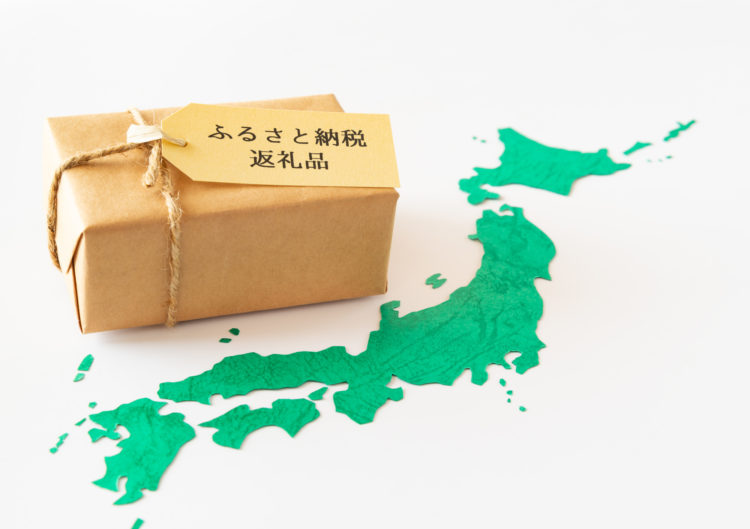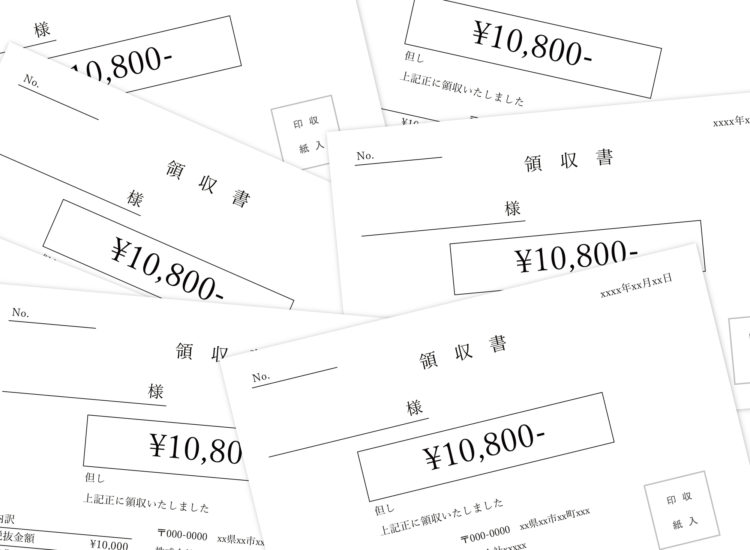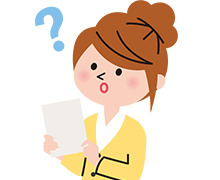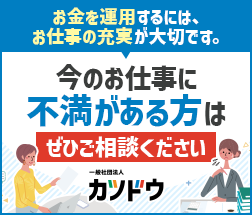「節税をして、払いすぎた税金を取り戻そう!」
こう言われると、サラリーマンでも自営業者でも興味をひかれるものです。
戻ってくるお金(還付金)は指定した銀行口座に振り込まれますから、奥さんに財布を握られている旦那さんなら、ちょっとしたへそくりをゲットすることもできます。
しかし、節税を目的にいろいろと工夫した結果が裏目にでることもあるんです。
大切なのは「この節税は本当に得か?」と考えること。そこを間違えると逆に損をすることもあります。
ここではそんな事態を事前に回避するために、「しないほうがマシなザンネン節税」を4パターン紹介します。
節税を目的に保険やふるさと納税を利用する
保険やふるさと納税が節税になるワケ
「生命保険に入ると節税にもなる」
「ふるさと納税を利用すれば、返礼品が手に入るうえに節税にもなる」
こんな話を聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。
生命保険には生命保険料控除という制度があり、払い込み金額から年間最高4万円の所得控除(※)が受けられます。
これ以外にも介護医療保険、個人年金保険に加入している場合もそれぞれ最高4万円ずつ控除が受けられるので、合計で最高12万円の控除が受けられることになります。
最高額の12万円の控除が受けられれば、例えば所得税率が20%なら2万4,000円の節税になります。
一方、ふるさと納税には寄附金控除という制度があります。
これは自治体に寄付をした合計金額から2,000円を差し引いた金額が、翌年収める住民税と所得税から差し引かれる制度です。
例えば宮城県の自治体に1万円を寄付して、返戻金として宮城県の牛タンを受け取った場合、美味しい牛タンが食べられるうえに、8,000円の節税になります。
(※)控除制度の仕組みについてしっかりと理解しておきたい人は、サラリーマンが節税を「本気で」始めるべき3つの理由を参照してください。
節税対策としての保険やふるさと納税の問題点
こう考えると、一見どちらも得をしているように思えるかもしれません。しかしもう一度よく考えてみましょう。
本当に生命保険に加入する必要はあったのでしょうか。保険はあくまで「万が一」のためのもの。
もし自分が亡くなっても経済的に困る人がいないのなら加入する意味はほとんどありません。
介護医療保険や個人年金保険にしても、日本はそれぞれ立派な公的保険がありますから、わざわざ民間の保険に入る理由はない可能性が高いでしょう。
またふるさと納税で節税できる金額には限度があり、それを超えた寄付は節税にはつながりません。
何も考えずに寄付を続ければ、本来欲しいわけではなかった返礼品が家のなかで山積みになるわ、節税にならないわ、損ばかりすることになります。
「必要のない、余計なもの」を買えば、当然損をします。保険もふるさと納税も、同じなのです。
節税を目的にiDeCoや不動産投資を始める
iDeCoや不動産投資が節税になるワケ
iDeCo(個人型確定拠出年金)や不動産投資など、節税効果を売り文句にする資産運用商品はたくさんあります。
特にiDeCoは国が主導で進めている制度だということもあり、節税効果が非常に高いことで知られていますよね。
以下はいわゆるiDeCoの三段階節税をまとめたものです。
- 拠出時、掛け金が全額所得控除になる。
- 運用時、運用によって生じる利益は非課税になる。
- 受取時、退職所得控除や公的年金控除を受けられる。
また不動産投資も節税効果が高い資産運用方法として知られています。
サラリーマンでも自営業者でも、不動産の借入金の返済や減価償却費を経費として計上することができるからです。
この経費を家賃収入から差し引いた金額が赤字の場合、赤字の分だけ所得が減るので節税ができるのです。
節税対策としてのiDeCoや不動産投資の問題点
ところが実は損をする場合もある?iDeCoのメリットと「落とし穴」でも解説したように、専業主婦などの所得税がもともと少ない人はiDeCoの節税効果は薄くなります。
加えてiDeCoのお金は60歳になるまで引き出せないため、突然の出費に対応できないというデメリットがあります。
また不動産投資の節税効果も実は時間が経つにつれて薄れていきます。
借入金や減価償却費は年々減っていくため、計上できる経費の額も年々減っていくからです。
経費の額が減るということは、不動産で黒字が出るということなので良いことなのですが、節税効果という意味ではどうしても薄くなっていくのです。
iDeCoも不動産投資も、投資による資産運用で長期的・安定的に収益を得るのが本来の目的です。
この部分を考えずにただ「節税をしたらお得だ!」というイメージで投資をはじめても、思うようなメリットは得られません。
さらにいえば、資産運用は大なり小なりリスクを背負うもの。必要な知識なしにはじめれば損をする可能性も十分あります。
節税効果を売り文句にする投資をする際に考えるべきは節税効果ではなく、「この投資で自分はどれくらい資産を増やせるのか」です。
くれぐれも目先の節税に目がくらまないよう注意しましょう。
配偶者特別控除内に収めるために配偶者の収入を調整する
配偶者特別控除の節税効果
配偶者特別控除は控除制度のなかでも節税効果の高いものの一つです。
この制度は配偶者の手取り額に応じて控除額が決まり、メインで稼いでいる人の手取りが900万円以下の場合、最大で38万円の所得控除が受けられるというものです。
所得税率20%の人が38万円の所得控除を受けられれば、節税額は7万6,000円。したがって他の制度と比べると節税効果が高いとされているのです。
ここで出てくるのが「○○○万円の壁」という言葉です。
2019年10月時点では99万円・106万円・130万円・150万円の壁があります。下表にこれらの意味をまとめておきましょう。
| 配偶者の「年収」の壁 | 壁を超えると…… | 壁を超えることによる手取りへの影響度 |
| 99万円 | 配偶者の収入が住民税の対象になる | 小 |
| 106万円 | 配偶者が社会保険に加入しなければならなくなる | 大(社会保険料の負担分、配偶者の手取りが減少) |
| 130万円 | 配偶者がメインで稼いでいる人の扶養(3号)から外れる | 大(社会保険料の負担分、配偶者の手取りが減少) |
| 150万円 | メインで稼いでいる人が、配偶者控除を受けられなくなる | 小(配偶者特別控除が段階的に受けられる) |
収入を抑えるより、稼いだほうが得
こうして見てみると、「やっぱり年収は106万円に抑えてもらおう」といった考えが思い浮かぶ人も多いでしょう。
もちろん育児や親の介護など、仕事量を抑えて得られるメリットがあるのなら、税金や社会保険料の面で一番手取りが多くなる年収に抑えておく意味はあります。
しかしもしそうしたメリットがないのであれば、実は配偶者にはどんどん働いてもらったほうが得することも多いのです。
例えば厚生年金に加入していれば、そのぶんの老後の世帯収入がアップします。
税金や社会保険料が高くなったぶんをリカバリーできる配偶者の収入は153万円以上とされていますから、200万円、300万円と稼いでいけば、それだけ生涯の世帯年収もアップします。
仮に年間の手取りが20万円増えたとしたら、30年間で600万円にもなります。
「配偶者の収入は○○○万円に抑えないと損をする」という思い込みだけで働く時間を少なくしてしまうと、長い目で見たときにとてつもなく大きな損をする可能性があるのです。
税金が減るからと経費を切りまくる
個人事業主は節税しやすい
最後に紹介するのはフリーランスや個人事業主のお話です。
個人事業主はその性質上、サラリーマンに比べて色々な支出を経費として計上することができます。
「クロヨン(9・6・4)」「トーゴーサンピン(10・5・3・1)」という言葉がありますが、これらは次のような意味です。
- サラリーマンなどは所得の9割を税務署に把握されている
- 自営業者などは所得の6割を税務署に把握されている
- 農家や漁師などは所得の4割を税務署に把握されている
- サラリーマンなどは所得の10割を税務署に把握されている
- 自営業者などは所得の5割を税務署に把握されている
- 農家や漁師などは所得の3割を税務署に把握されている
- 政治家は所得の1割を税務署に把握されている
つまり自営業者は5〜6割程度しか所得を把握されていないため、サラリーマンに比べて節税しやすいということです。
もちろんこれはざっくりとした数字にすぎませんが、一定以上の差があるのは確かです。
そのため「業務用のパソコン」「会議のための飲食費」「レンタルオフィスの賃料」などをどんどん増やしていけば、自ずと支払う税金を少なくすることができるのです。
余計なものを買えば損をするのは同じ
しかしこれも冒頭の保険やふるさと納税と同じで、「必要のない、余計な出費」になれば意味がありません。
例えば税率10%の個人事業主が30万円のパソコンを経費として計上すれば、たしかに3万円の節税になります。
ところが30万円のパソコンではなく、20万円のパソコンでもスペックとしては十分だった場合、3万円は節税できても30万円−20万円−3万円=7万円は損しています。
まさに本末転倒。余計な出費です。
このように税金が減るからと何も考えずに経費を切りまくると、結果的に損をしてしまう可能性があるのです。
まとめ
節税はすべてが得につながるわけではありません。
一見得をしたように思える節税も、より広い視野で考えると損をしているというパターンも意外とあるんです。
税金を払いたくないのはみんな同じです。でも日本に住んでいる限りは、日本の税制度を受け入れるしかありません。
節税はそのなかでできる、ちょっとした工夫にすぎません。
「節税」という目先の利益にとらわれず、「ここで節税することで本当に得になるのか?」をよく考えたうえで、自分はどうするかを決断しましょう。